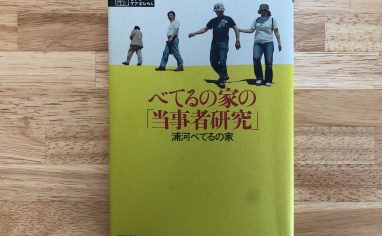どうすれば「創造性」を育てることができるのか?
(本日のお話 3504字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は2件のアポイント。
その他、夕方から家族会議にて「健全な子育てに関わる生活リズムのルールについて」の会議(?)でした。
私と妻で対応方法や、より好ましいルーチンを定義しておいたほうが、
色々とメリットが多そうだよね、ということで話し合いをしましたが、非常に有意義な時間になりました。
たまにはこういう会話も大事ですね。
*
さて、本日のお話です。
本日は「強みの育て方・活かし方」に関連する論文をご紹介させていただきます。本日のテーマは『創造性(Creativity)』の育て方・活かし方です。
▽▽▽
ちなみに『創造性(Creativity)』とは、「新規性」と「有用性」を持つアイデアや洞察を生み出す能力と定義されています。そして、これはAIでは再現できない能力として、昨今注目を集めています。
そんな、「21世紀のコンピテンシー」とも呼べる「創造性」を高めるにはどのような方法があるのでしょうか? 今日は日本の新しい論文から知見をご紹介できればと思います。
それではどうぞ!
――――――――――――――――――――
<目次>
今回の論文
「創造性」を生み出すもの
創造性の2つの思考法
創造性の2過程モデル
「メタ創造性」という新しい考え方
本論文のポイント
研究の概要
研究1(方略選定)
研究2(創造性との関連検討)
研究3(高校生への介入実験)
まとめと感想
――――――――――――――――――
=====================
<今回の論文>
What Strategies Enhance Creativity? — Relationship Between Meta-Creativity and Creativity どのような方略を用いると創造性が向上するか? ――メタ創造性と創造性の関係――
著者:Miki Toyama(University of Tsukuba)
ジャーナル:教育心理学研究, 2024年
=====================
■「創造性」を生み出すもの
先行研究から、「創造性」を生み出すものは、2つの思考方法と2つの認知プロセスがあると考えられています。どちらも2つなので、やや混乱しそうなのですが、聞いてみるとなるほどな~、というものです。
以下紹介いたします。
◎創造性の2つの思考法
まず1つ目ですが「創造性を生み出す思考法」です。
創造的な問題解決には「拡散的思考」と「収束的思考」の2つの思考法があるとされています。
以下ポイントを簡単に説明します
*「拡散的思考」
新しいアイデアを多く生み出す思考方法。
拡散的思考につながる3つの側面が以下の要素である。
1.思考の流暢性(次々と数多くのアイデアを生み出せる)
2.思考の柔軟性(既存の思考にとらわれず考えることができる)
3.思考の独創性(アイデアの非凡さや稀さ)
*「収束的思考」
現在持っている情報から1つの解を導き出す思考方法。
一般的には「拡散的思考」のほうが“創造性”という言葉からイメージしやすいですが、現在持っている情報をもとに収束的思考で答えを導き出すプロセスも含まれます。
◎創造性の2過程モデル
次に、創造性を生み出す認知プロセスについてです。これは「創造性の2過程モデル(Dual pathway to creativity model)」と呼ばれており、「認知的柔軟性」と「認知的持続性」の2つで構成されます。以下で簡単に解説します。
<創造性の2過程モデル>
*「認知的柔軟性」
カテゴリーをまたぐがような概念の情報処理を一度に行うこと。
視点を切り替えることが要求され、カテゴリーや概念間の新しいつながりを発見することができるため、創造性につながることが研究で実証されている(Forster & Danneberg, 2010; Zhang et al, 2020)。
*「認知的持続性」
少数の概念に対して、深く考え続ける(持続的に考える)こと。
注意力を集中させること、粘り強さや長時間の努力をすることで、創造的な結果がもたらされることも研究で示されている。
なるほど、確かに「創造性」には、様々なアイデアをつなげる「柔軟性」も必要です。また、粘り強く探求することで新しいアイデアが生まれる側面もあるため、「持続性」も創造性のために重要というのは納得感がありますね。
◎「メタ創造性」という新しい考え方
ここで、もう一つ紹介いたします。ここで創造性研究において新しく注目を浴びている概念が『メタ創造性』です。
*メタ創造性の定義
メタ創造性とは、「創造性を育む可能性のある方略を意図的に実行すること」(Mevarech, 2019)と定義されています。”メタ(Meta)”とは、高次元の、超越したという意味で、視点を外側から見ることを指します。つまり、自分自身が創造性を持っているかどうかを俯瞰するスタンスを「メタ創造性」と呼ぶようです(統一された見解はまだありません)。
*メタ創造性のポイント
・メタ創造的モニタリング
自分の創造性における長所や短所を理解し、それを俯瞰的に意識すること
・メタ創造的コントロール
創造性を育む可能性がある方略を意図的に実行すること。具体的には「思い込み・前提を疑うこと」と「視点を変えること」(Runco, 2015)が挙げられます。
この「メタ創造性」の考え方(思い込み・前提を疑うこと)によって、実際の「創造性」にも影響があるだろう、、、そのように考えられているようです。
■本論文のポイント
さて、前置きがだいぶ長くなりました。今回ご紹介の論文について、ここまで話を前提として、ポイントを以下まとめます。
・本研究は、「創造性」と「メタ創造性」の関連を体系的に分析することを目的としている。
・特に「メタ創造的コントロール」(「創造性」を育む可能性のある方略を意図的に実行すること)に焦点を当てた。
・研究1では、「創造性」を育成する方略を選定し、研究2ではそれらの方略が「創造性」と関連することを実証した。
・研究3では、高校生を対象に「メタ創造性」への介入が「創造性」を向上させるかを検証し、肯定的な結果を得た。
・これらの結果から、教育現場における創造性育成プログラムの重要性とその実践可能性が示唆された。
とのことです。特に本論文では「メタ創造性」を確認する因子分析結果などもあり、また介入の結果も示唆深いもの興味深いものでした。
■研究の概要
では、具体的にどのような研究をおこなったのか。より詳しく見てみたいと思います。方法と結果について、以下まとめてみます。
◎研究1(方略選定)
<研究方法>
・対象: 成人415名(18-60歳、男性200名、女性213名)。
・創造性課題: 「用途テスト(Unusual Use Test: UUT)」と「遠隔連想テスト(Remote Associates Test: RAT)」を使用した。
・方略選定: 認知的柔軟性と持続性に基づき、15項目を因子分析で選定(例: 「多角的な視点」「粘り強く取り組む」など)。
<結果>研究1からの示唆:「メタ創造性」は3因子構造だった。
15の方略項目が「メタ持続性」「メタ柔軟性」「メタ連想・関連づけ」の3因子に分類された。因子ごとの内的一貫性は良好(α係数0.70以上)。
◎研究2(創造性との関連検討)
<研究の方法>
対象: 成人655名(18-60歳、ランダムにUUTまたはRATに割り当て)。
分析: メタ創造性と創造性(流暢性、柔軟性、独創性、正答数)の相関を検討した。
<結果>メタ創造性の持続性・柔軟性は、「創造性」と相関があった
・「メタ持続性」「メタ柔軟性」は「創造性」全般と有意な正の関連があった(流暢性: r=.32、柔軟性: r=.20 など)。
・「メタ連想・関連づけ」は一部の指標(流暢性: r=.28)で有意な関連を示したが、柔軟性や独創性とは関連が薄かった。
◎研究3(高校生への介入実験)
<研究の方法>
・対象: 高校生291名(16歳前後、男女比ほぼ均等)。
・デザイン: 対照群(一般的な創造性説明のみ)、持続性介入群(粘り強さを強調)、柔軟性介入群(視点転換を強調)の3群に分け実施。
・評価: 創造性(流暢性、柔軟性、独創性)をUUTで測定した。
<結果>持続性と柔軟性への介入により創造性が高まった
・持続性介入群と柔軟性介入群は、対照群に比べ創造性が向上した(流暢性: 持続性介入群M=3.73、対照群M=2.30、p<.001)。
・柔軟性や独創性についても同様の傾向が観察されたが、効果サイズは流暢性に比べ小さかった(柔軟性: f=.18、独創性: f=.15)。
■まとめと感想
日常から使っている「創造性」という概念に、2つの思考方法、認知プロセス、メタ創造性などの要素にわけることで、「創造性」についての知識がぐっと増えたように思います。
活用方法として、考え方として「思い込み・前提を疑うこと」と「視点を変えること」は「メタ創造的コントロール」のアクションとしてすぐに取り入れることができるでしょう。
また、論文には言及されていませんでしたが使いやすい方法としては「拡散的思考」や「柔軟性」を促すための「マインドマップの作成」も役に立つと思われます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>