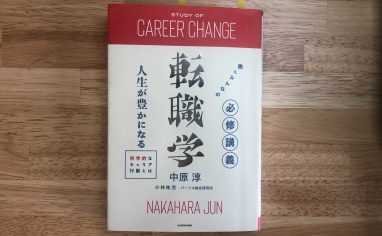「オレとアイツの差」はどこで生まれるのか? ―読書レビュー『遺伝マインド』#2
(本日のお話 2351字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は2件のアポイント。
また足をなまらせないために、マンションの非常階段の上り下りをしておりました。
せっかくフルマラソンを出たので、その筋力を維持するには、ある程度動かしたほうがよいのです。
野辺山ウルトラマラソンまで、46日。
*
さて、本日のお話です。
昨日より「行動遺伝学」を取り上げた書籍『遺伝マインド』の読書レビューをしております。
しばしば耳にする「人間は遺伝か?環境か?」という問いに、行動遺伝学の研究からわかってきたことを、一般の人にわかるように説明された本です。(専門書だけど入門書、みたいなイメージ)
本日は「第1章 遺伝子と多様性」より、学びを共有させていただければと思います。
それでは、どうぞ!
―――――――――――――――――――――
<目次>
40億年の遺伝子の旅
遺伝子は「ある条件下」で発現する
「オレとアイツの差」はどこから生まれるか
まとめ
―――――――――――――――――――――
■40億年の遺伝子の旅
この第1章では「そもそも遺伝子ってなんだ?」という問いを考えます。
そして、そのためには「遺伝子の歴史」に触れなければなりません。なんとなく高校の生物の授業みたいになりますが、ご容赦ください。
さて、遺伝子のはじまりは、40億年前。RNA(リボ核酸)が生まれた時からスタートします。そこから二重らせん構造の「DNA」になり、自らのコピーを生み出せるようになりました。
そして遺伝子は「遺伝子の乗り物」として、この世に存在する「無数の生き物」(現在は140~170万の生物種があるそう)を作り続けてきました。こうした過程を「進化」と呼びます。
こうすると、「遺伝子が生き残ろうとした」みたいな目的論になりますが、もっと根源的に「遺伝子が存在しているから、そもそも生物が存在している」という方が正しいです。
この世界は「遺伝子」によって作られている…のかもしれません。
■遺伝子は「ある条件下」で発現する
遺伝子は、4つの組み合わせによる配列でできています(A:アデニン、T:チミン、C:シトシン、G:グアニン)。
DNAを構成する塩基対の数は「30億」あります。
これがいわゆる、ヒトゲノムと呼ばれる、人間1人を作る設計図であり、遺伝情報の全てです。
そして、30億の塩基対の中には、”始まりの暗号(+ATG)と、終わりの暗号(*TAA,TAG,TGA)”で構成される「意味ある配列」が存在しています。そしてこの「意味ある配列」がタンパク質などをコードする「遺伝子(gene)
とされます。この数が「2万2000個」あるそうです。
そして”ある条件下”のもとで、遺伝子における「意味ある配列」が読み出され、翻訳されることで「遺伝子が発現」されます。例えば、こんなイメージです(生物の授業みたいですが、雰囲気だけ感じていただければと)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例:血糖値が上がったときに起こる遺伝子発現(インスリン遺伝子の発現)
1.血糖値が上昇
2.膵臓のβ細胞が刺激を受ける
3.インスリン遺伝子の転写が促進される
4.インスリンmRNAが作られる
5.リボソームで翻訳が行われアミノ酸配列としてインスリンが合成される
6.インスリンが分泌され、血糖値を下げる作用を発揮
※「ある条件(血糖値の上昇)」という外部刺激によって、遺伝子が発現し、タンパク質(インスリン)が作られるという流れが起こる
(ChatGPTによる具体例の解説)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ポイントは、「遺伝子の発現は常に起こるわけではなく、細胞の状態や外部環境に応じてオン・オフが調整される」ということです。(エピジェネティック調節、などと言われています)
■「オレとアイツの差」はどこから生まれるか
すでに塩基対の30億の中に、意味ある配列である2万2000の遺伝子がいる。
途方もない数字で、想像を超えていますが、これが生命の設計図で、あらゆる生物はこの「A:アデニン、T:チミン、C:シトシン、G:グアニン」出できているのは、改めて興味深いです。
ちなみに、「人とチンパンジー」は、違うけれど似ています。
人とチンパンジーの塩基配列は「98.77%」同じです。
また、「オレとアイツ」も、違うけれど似ています。
オレとアイツの塩基配列は「99.9%」同じです。違いはわずか0.1%です。
・・・とすると、例えば私(紀藤)と大谷翔平の違いもわずか0.1%!
ほぼ同じです。でもツッコミが聞こえます。「いや、明らかに違うだろw」と。
では、この違いは、どこから生まれるのか?
それが「0.1%の重み」です。
塩基対の30億ある遺伝情報の中の0.1%の違いは「300万の違い」となります。これが意味ある配列の「2万2000」の遺伝子におけるATCGの文字の違いとして組み込まれます。たった一文字違うだけで、異なる働きを持つアミノ酸が生み出され、異なる出力がされます。0.1%は遺伝子の中では大きく違ってくるのです。
これが肌の色とか、髪の色、目の色などに影響を与え、個体差を生み出しています。
■まとめと感想
遺伝子の歴史は、40億年。
ホモ・サピエンスの歴史は、10~20万年。
遺伝子を発見したのは、150年前。
遺伝子の分子構造にたどり着いたのが、60年前。
この長い歴史の中で、遺伝子が生物に与える影響が検討されたのは、100年ほどの歴史です。遺伝子や人の歴史を考えると、とても短いです。
一方、人はもっと長い時代をかけて「文化」を育んできました。だから、「人の先祖はサルだった」という話も、当時は受け入れがたかったのです。
「遺伝子が行動に影響を与える」というのも、そういう意味では、まだまだ直感的にしっくりこない、ということもあるかもしれません。
▽▽▽
また「人間は特有の遺伝子として「利他的な遺伝子」がある」というのも興味深い話でした。「自分が生活をするために仕事をする(利己的)」だけど「それが誰かの役に立っている(利他的)」というのが、種を存続させるために、全体として組み込まれているのが特殊である、という話でした。
ますます不思議な遺伝子の話ですが、現在わかっていることを紐解いていくのは、興味深いものだなと感じている次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>