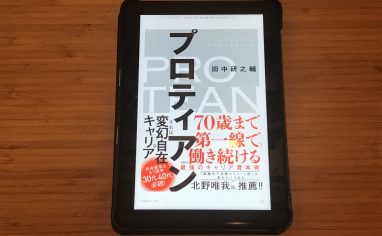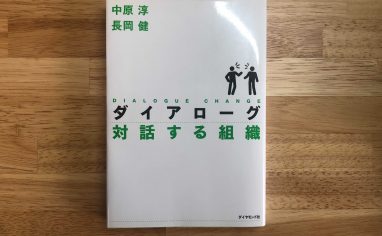「自分が変わりたい」と思うことすら遺伝子が影響している?! ―読書レビュー『遺伝マインド』#7
(本日のお話 3573字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日も引き続き、立教大学のビジネスリーダーシッププログラム(BLP)のウェルカムキャンプのDAY2でした。高校の文化祭のような熱気にほだされて、焚き火が燃えるような熱量と、その後の炭になった感覚を同時に味わいました(特に何かしたわけではないのですが)。
これからが本当に楽しみです。
自分も関わった仲間と、そして自分自身も含めて、成長に寄与できるよう、頑張りたいと思いました。
*
さて、本日のお話です。
先日より、遺伝子が心や行動に与える影響を科学する「行動遺伝学」をテーマに学びを共有しております。
本日は「第5章 環境のはなし」より、遺伝子に影響を与える環境について、考えを深めていきたいと思います。
それでは、どうぞ!
―――――――――――――――――――――
『遺伝マインド --遺伝子が織り成す行動と文化』
―――――――――――――――――――――
■行動遺伝学の3つの法則
さて、以前も紹介しましたが、本書の中心となる「行動遺伝学の3つの法則」は以下のようなものです。
1.あらゆる心理的特徴には遺伝の影響が見られる
2.共有環境の影響はまったくないか、あっても相対的に小さい場合が多い
3.非共有環境の影響が大きい
――この3つです。
何かしらの成果が生まれるとき、それは「遺伝子、共有環境、非共有環境」の三者がそれぞれの影響度を持って関連し合っている」と考えられており、私たちの認知能力やパーソナリティにまでその影響は及びます。
■遺伝子に影響を与える「2つの環境」とは
さて、その中で「環境」と名がつくものに、「共有環境」と「非共有環境」があります。
まず「共有環境」ですが、たとえば双子がいたとします。同じ家に生まれ、同じ食事をし、同じ学校に通い、似たような教育スタイルで育てられる。これが「共有環境」に当たります。
次に「非共有環境」ですが、その双子が違う部活に入ったり、起きる時間が違ったり、観るテレビ番組が違ったり、読む本が違ってくる。そういった細部の違いは、同じ家庭内にあっても「非共有環境」として存在します。
この両者が遺伝子と相まって、パーソナリティや認知能力に様々な影響を与えます。
そして繰り返しますが、行動遺伝学の3つの法則で、2.「共有環境」の影響はまったくないか、あっても相対的に小さい場合が多い、3.「非共有環境」の影響が大きい とあるのが、非常に興味深いところです。
■親の影響より、仲間の影響?
ちなみに、発達心理学では長らく「親の育て方がもっとも重要である」と信じられてきました(「養育仮説」と呼ばれます)。
しかし、心理学者のジュディス・リッチ・ハラスは「親の養育を絶対視する考えは迷信にすぎない」と述べました。(Harris, 1995)加えて、「子どもにとって重要な環境とは家庭ではなく、どのような仲間集団に属するかである」とする集団社会化仮説を述べます。
これはまさに「共有環境」=「親の育て方」よりも、「非共有環境」=「どんな友達と付き合ったか」の影響の方が大きいということで、実に納得いく話に思えます。
▽▽▽
また、それを支持するような実験として、他の一卵性双生児を対象とした研究では、以下のような結果が報告されています。
―――――――――――――――――――――
“同じ家庭で育った一卵性双生児のパーソナリティの相関係数は0.49、別々に育った一卵性双生児は0.50。つまり、ほとんんど差がない。”(BouBoubard et al, 1990)
―――――――――――――――――――――
つまり、「遺伝子が同じであれば、同じ家に育とうが、別々に育とうが、性格の類似度は変わらない」ということです。
余談ですが、この話を聞いて妻は「逆に肩の荷が降りた気がする」といっていました。「養育仮説」は時に親の強いプレッシャーになり得ますので、こういう情報がポジティブに作用することもあるのでしょう。(ちなみに、うちの母は「自分はあんたを放置していたけど、勝手に育った」と言っていました(苦笑))
■「親の育て方」の意味とは
ただし、ここで重要な点があります。たとえ性格や行動特徴が遺伝によるものであっても、人は「自分がどうしてそうなったのか」を語る際に、「親の影響」が理由として挙げられる傾向があるのです。
たとえば、こんな事例があります。ある几帳面な人が「母親が几帳面だったから」と語り、同じように几帳面な別の人が「母親がだらしなかったからこそ自分は几帳面になった」と語るなど。ちなみにこの二人、同じ遺伝子を持った一卵性双生児だったそう。なんとも興味深い話です。
いずれにせよ、「自分がどうしてこうなったのか?」というアイデンティティの形成に、親がどうあったのかというのは、物語を作るための重要なパーツになるわけです。そういう視点で親の育て方が重要というのは、新しい視点だと思いました。
■「自分を変えたい」すら遺伝子の声である?!
私がこの章の中でも特に心を動かされたのは、「自分の心や行動を変えたい」という欲求がどこから生まれてくるのか、という問いかけでした。
その欲求には、大きく2つの出どころがあるとされています。
―――――――――――――――――――――――――――――――
<心や行動を変えたいと思う理由>
1.他者からの要求によるもの(外生的行動変容欲求)
2.自分自身から湧き上がるもの(内生的行動変容欲求)
―――――――――――――――――――――――――――――――
1は、学校で「数学ができるようになれ」と求められる。職場で「営業成績を上げろ」と言われる。好きな人から「その優柔不断な性格が嫌」と言われ、変わろうとする——そんなパターンです。
2は、「もっと積極的になりたい」「人前で堂々と話せるようになりたい」「注目されたい」といった、自分の内側から湧き上がる変化への衝動です。
▽▽▽
ここでまたひとつ、深く考えさせられる視点が登場します。この「自分自身から湧き上がった変化欲求」すらも、実は遺伝の影響を受けている可能性がある——というの話です。
たとえば、「自然と好奇心が湧いてくる」「自然と熱意を持てる」「自然と批判的に考える癖がある」——こういった“心の傾き”自体が、もともと遺伝的に備わったものである、と述べるわけです。
■「遺伝子の声」がする環境を選ぶこと
そして重要なポイント「行動を変えたい」という欲求が、外側からの強制で起こる場合と、内側からの願いで起こる場合とでは、その意味がまるで違ってくる、ということです
外側から変化を求められるとき、自分の遺伝的な傾向と環境が衝突して、息苦しさを感じる可能性があります。でも、内側からの変化欲求(遺伝子の声)であれば、その環境はむしろ「自分がもった遺伝子の種」が花を咲かせるための栄養の場になり得ます。
▽▽▽
とすると、大切なのは「自分自身を理解すること」だと私は思います。
それが、内側にぐっともぐり研究をじっくりと探求する方が好きなのか、外側に開いて色々な人と関わることを楽しむのか…
自分の内側からやってくる見えづらい遺伝子の声に耳を傾けて、自分がフィットする環境が何かを選ぶこと。そこではじめて、自分が本来持っていた可能性が、のびのびと発現する可能性がある、と思います。
遺伝か環境か、という二項対立ではなく、両者のマッチングの妙。そこに、私たち一人ひとりの生きやすさが宿っているように感じた次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>