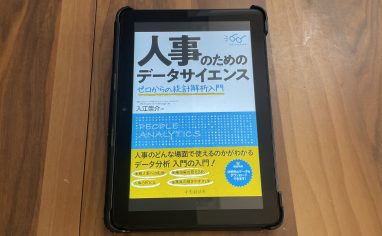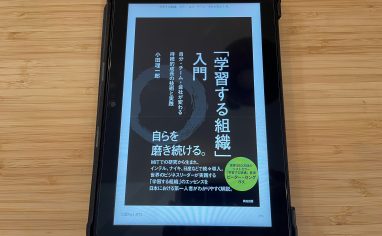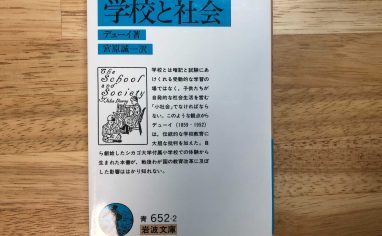強みの研究は「キャラクター」から「パーソナリティ」へ
(本日のお話 2856字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
本日は「強み研究」の論文のご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、「性格の強みを”パーソナリティ科学”という大きな傘の下に統合してはどうか」と提案する、この分野の未来に向けて提唱した理論レビュー論文です。
なんとなく感じつつも、言葉にできなかった「確かにこういう疑問あるなあ」と思う感覚を、議論の舞台にあげるような論文で納得感を覚えながら読みました。ちょっとマニアックですが、面白い論文でした。
ということで、さっそく中身を見ていきましょう!
■目次
今回の論文
本論文のポイント
キャラクターストレングスからパーソナリティストレングスへ
強みの「SaMモデル」とは?
強みの三次元モデル「保有・自覚・使用」
実現された強み vs 未実現の強み
まとめと個人的な感想
■今回の論文
――――
タイトル:Integrating psychological strengths under the umbrella of personality science: Rethinking the definition, measurement, and modification of strengths(心理的強みをパーソナリティ科学の傘下に統合する:強みの定義、測定、修正の再考)
著者:Fallon R. Goodman, Todd B. Kashdan
所属:George Mason University
雑誌名:The Journal of Positive Psychology、2019年
――――
■本論文のポイント
まず、本論文の大まかな主張を整理すると、以下のような話です。
・ポジティブ心理学の隆盛により「強み」の研究が拡大するも、定義・測定・介入に課題が残る。
・強みは道徳的価値ではなく、パーソナリティ特性の適応的側面として再定義すべきと提案。
・文化相対性の観点から、道徳性に依拠した定義は再検討が必要。
・強みは「保有」「自覚」「使用」の3次元モデル(SaM)で理解されるべき。
・SaMモデルは臨床応用の可能性があるが、科学的エビデンスの蓄積が今後の課題。
とのことです。
■キャラクターストレングスからパーソナリティストレングスへ
この論文の主張は、一言でいえば「性格の強み(キャラクターストレングス・ファインダー)を、道徳性から切り離し、パーソナリティ理論に組み込もう」というものです。
キャラクターとパーソナリティ、どちらも「性格」と訳されますが、そのニュアンスは若干違っています。イメージはこんな感じです。
キャラクター(Character):道徳性や価値観と深く結びついた人格の側面。
パーソナリティ(Personality):感情・思考・行動の一貫したパターンとしての個人の特性全体。
つまり、「キャラクター」は「良さ(美徳)」を前提とした概念であり、「パーソナリティ」はより中立的かつ科学的な構造としての枠組み、とされています。
▽▽▽
そして「性格の強み」の研究は、キャラクターストレングスであり、VIAを代表ツールとして活用されてきました。これは当初「美徳(Virtue)」という道徳的価値と強く結びついて設計されているものです。その歴史は、ポジティブ心理学の黎明期における、DSM(精神障害の診断マニュアル)へのカウンターとしての意味合いも強いものでした。
しかし著者らは、「強みを“道徳的なもの”として定義し続けることに限界がある」と指摘します。たとえば、文化によって美徳の意味合いが異なるため、普遍的な科学モデルとしては不利に働くのではないか、という反論も述べています。
そのため、より多くの研究がされている「パーソナリティ」の科学のビッグファイブや、自己調整、目標志向性などの概念も含めて検討することが、これからの研究に必要なのでは、と提唱したわけです。こうすると、VIAだけでなく、CliftonStrengthsやStrengths Profileといった他のアセスメントも含めて、統合する方向ができるかもしれません。
また余談ですが、こうした「キャラクターからパーソナリティへ」と移行して作った強みのテストは、2023年日本の研究者等によって作られた「Character Strengths Test24」などがまさにそうだと感じました。
■強みの「SaMモデル」とは?
また、論文内で提案されているもので「SaMモデル(Strengths as Moderators model)」なるものがありました。
これは、強みが精神障害の症状と日常生活の機能との“関係性”を緩和することもあれば、悪化させることもある、という立場です。
◎論文に出てくる印象的な事例:
・忍耐力が強すぎる男性が、うつ病によって恋愛関係に悪影響を及ぼした
・妻との葛藤があるにもかかわらず、「諦めない強さ」が働いて関係を修復できなかった
・高等教育を受けていないが、持ち前の忍耐力でビジネスを成功させた
ポイントは、「強み」は常にポジティブに作用するとは限らず、状況や組み合わせによって、良くも悪くもなるという点が強調されているところです。
これも先述の「キャラクター(美徳を含む)」から「パーソナリティ(性格)」という意味合いに変えたほうがよいのでは、という背景にもなっているようです。
■強みの三次元モデル「保有・自覚・使用」
またもう一つ興味深かったのが、「強みの三次元モデル」です。
1.保有している強み
2.自覚している強み
3.実際に使用している強み
この3つは同じではなく、それぞれを区別して捉えることが重要だというのです。
このあたりの話は、Strengths Profileの考え方に紐づいていますが、Linleyによる以下の考え方が具体的に紹介されています。
・実現された強み vs 未実現の強み
・実現された強み:頻繁に使われ、有益であり、使うと活力が湧く
・未実現の強み:潜在的には強みだが、ほとんど使われていない
実現された強みを使っているとき、人はフロー状態になり、自然と優先順位もその活動に向かう。アイコンタクトの増加や話す速度の上昇といった身体的なシグナルも現れるそうです。
また、「強みの使用と自覚」については、Strengths Use and Knowledge Scaleといった測定ツールも紹介されていますが、こうした「保持」「自覚」「活用」を明確に分けて論じることが重要とのことです。
■まとめと個人的な感想
この論文を読んだ一番の感想は、「強みとは、人の行動傾向の一部であり、それが道徳性と直結する必要はない」という著者らの提案です。
また、「どんな状況でもポジティブに作用するとは限らない。その人が持つ性格として、他の特性や環境とともに理解すべき」というメッセージも、共感するものでした。
このような視点は、これまで私自身が感じていた違和感「性格の強みポジティブすぎ問題」(=性格強みは“美徳”という概念が強すぎて、やや人を選ぶ)と一致しており、非常に納得のいくものでした。
研究としては実験的ではなく、あくまで理論的な整理に留まる論文ですが、今後の「強み」研究におけるひとつのマイルストーンになるのではと感じました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>