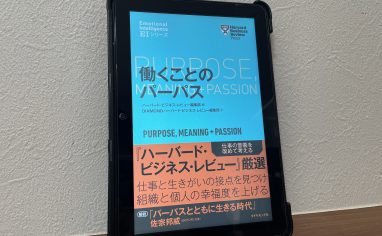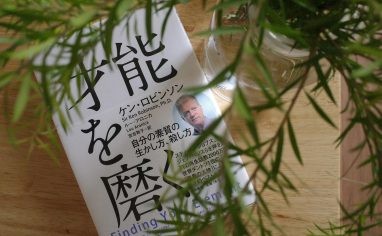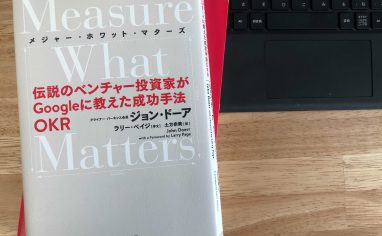ステータスが低い人ほど「専門用語」を使いたがる
(本日のお話 2254字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、リモートでサポートいただいている弊社のスタッフさんと、
そのパートナーの方と家族でランチでした。
また出版に向けた企画作成、研修プログラムの作成、
夜は7kmのランニングなどでした。
*
さて、本日のお話です、ハーバード・ビジネス・レビュー2021年10月号にて『専門用語の心理学』というタイトルで、ある論文が紹介されていました。
論文の内容は「ステータスが低いほど、専門用語を使いたがる」というものです。シンプルに伝えればわかるのに、なぜ複雑な専門用語を使ってしまうのか・・・。ここには様々な心理が潜んでいるようです(ギクリ)。
それでは、早速内容をみてまいりましょう!
=================================
<今回の論文>
タイトル:『Compensatory Conspicuous Communication: Low Status Increases Jargon Use』(補償的顕示的コミュニケーション:低い地位は専門用語の使用を増加させる)
著者:Zachariah C. Brown, Adam D. Galinsky
ジャーナル:Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2020年11月
=================================
■1分でわかる本論文のポイント
・「文章を書くときには、わかりやすく書くべき」と言われるが、ときに専門的な複雑な言葉が、たくさん使われることがある。
・本研究において、研究者らが、6万4956本の博士論文と修士論文のタイトルを分析した。そして米国大学の年間大学ランキングに基づいて、ステータスを高いor低いにわけて、その傾向を調べた。
・分析の結果、「ステータスが低い大学の著者ほど、複雑な専門用語を多用する傾向がある」ことがわかった。また、「省略した頭文字のみの言葉を使う傾向」も多かった。
・参加者に「なぜそのような言葉を選んだのか?」と聞くと、ステータスが低いと思っている人は「読み手から評価されたい」と思っていたことがわかった。(ステータスが高い人は「自分の考えを明確に表現する」を重視していた。
という内容でした。
■本研究の概要
本研究の概要や方法について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
ちなみに、タイトルにもある「ジャーゴン」とは「専門用語」のことです。
もう少し丁寧に言うと、「特定の職業や分野で使われる特別な言葉や言い回し」のことであり、もともとは情報を分かりやすく伝えるためや、グループの仲間意識を高めるために使われるものであったとのこと。
(例えば、ASAP(As soon as Possible)で!、なる早でお願い!などなど)
◎研究の背景
従来、ジャーゴン(専門用語)は特定の職業やグループ内での効率的な情報交換手段とされてきたが、本研究では、低地位の人々が自分のステータスを補償するためにジャーゴンを使う行動に焦点を当てている。社会心理学的文脈での地位補償行動の一環として、この言語使用がどのように発生し、どのように機能するかを明らかにすることを目的とする。
◎研究方法と結果
論文では、以下のような内容の研究を行ったとされています。
(1)学位論文タイトル分析
・方法: 64,000件以上の学位論文タイトルを、著者の所属学校ランク別に分析。高ランク校と比較して、低ランク校の著者がより多くのジャーゴンを使用しているかを調査した。
・結果: 低ランクの学校の著者は、高ランクの学校の著者よりも専門用語を多く使用していた。
(2)低い地位を感じる状況下での実験
・方法:地位感覚を操作する実験(例:「低い地位を感じる状況」を作り出す条件設定)をした。その上で実験参加者に架空の文章や会話を作成させ、ジャーゴン使用の傾向を測定した。
・結果:地位を低く感じる条件下では、参加者が意識的にジャーゴンを多く用いる傾向が確認された。これは、自己の地位を補償する意識が影響していることを示唆。
(3)対話内容の会話分析
・方法:地位操作を受けた参加者が実際に行う対話を分析し、ジャーゴン使用頻度を測定した。
・結果:実験参加者(地位が低いと感じている)は、リアルタイムの対話中にもジャーゴンを多用しており、ジャーゴン使用が意図的であることを示す証拠が得られた。
(4)参加者の動機の確認
・方法:地位感情、ジャーゴン使用、聴衆の評価への意識を含む媒介変数を分析した。
・結果:ジャーゴン使用の増加は「聴衆の評価を得たい」という動機によるものであり、明確な情報伝達を重視する場合には減少する傾向が見られた。
◎議論
本研究では低い地位にある個人が、他者からの評価を気にするあまり、コミュニケーションの明確さよりもジャーゴン使用を優先する傾向があることを示した。
本研究は、これまであまり注目されてこなかった「地位補償」と「言語使用」の関連性を初めて実証した。
さらに、消費行動における顕示的な行動(例: 高級ブランド品の購入)と同様に、言語選択も顕示的である可能性を示唆している。
■まとめと感想
本研究について、うわー、なんだかわかる・・・と反省してしまいました
自分も、密かに「学歴コンプレックス」を感じるものがあります。
大学院で学んで、そうしたものが晴れるかと思ったら、やはり染み付いた、自らの「ステータス低いアイデンティティ」は、胸の奥底で体育座りをしているようです。
しかし、「すごい人」と思われたくて専門用語を使っても、見る人からみれば、その心理を含めて、なんとなくわかるもの。
大事なことは「すごい人」と思われることではなく、相手に届けることですし、自分のそうした「欲求(地位を高めたい・すごいと思われたい)」に振り回されず、適切なコミュニケーションを取れるようになりたいものだ、そんなことを感じた次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>