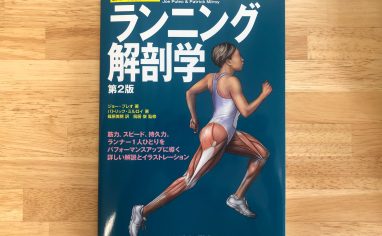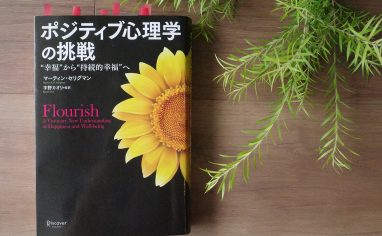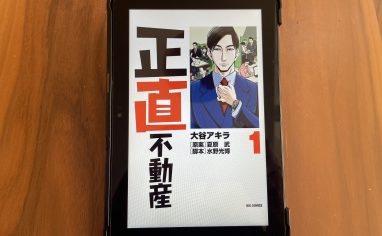「深い会話」ができないのは、浅い会話がよいという勘違いから生まれる
(本日のお話 3956字/読了時間6分)
■こんにちは。紀藤です。
本日はハーバード・ビジネス・レビュー2023年4月号の『スモールトークを超えるには』というタイトルの記事をご紹介いたします。
人と「深い会話」をすると、親密な関係が生まれる、幸福度が高まるなど、ポジティブな効果があることが研究でわかっています。
とはいえ、なかなか気軽に深い会話はしづらいもの(特に親しくない人とは)。その理由は「急にそんな深い会話されても、相手も困るんじゃね・・・?」と思ってしまうからです。
相手はそんなに深い会話を望んでいない、もっと気軽なトークを望んでいるだろうという見立てから、私達は表面的な会話を選択しがちです。
ですが、論文の7つの実験でわかったことは、違いました。予想に反して「深い会話をすることでポジティブな結果を得やすくなる」「深い会話を阻むのは、相手が(深い会話を)望んでいないという誤解によるものである」ことがわかりました。
日常会話で、相手に一歩飛び込んでみる勇気を与えてくれる、とても実践に活きる内容の論文と感じました。ということで、早速中身を見てまいりましょう!
==============================
<今回の論文>
『Overly Shallow?: Miscalibrated Expectations Create a Barrier to Deeper Conversation』(浅すぎる会話: 誤った期待が深い会話への障壁を生む)
著者:Michael Kardas, Nicholas Epley
ジャーナル:Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition, 2021
==============================
■1分でわかる本論文のポイント
日常会話の約半分は表面的で浅い内容にとどまっている。
一方、深い会話には、心理的負担の軽減や親密な関係の構築、幸福感の向上といった利点がある。そのため「どうやって深い会話を増やすのか」というテーマの書籍が人気を集めている。
深い会話を避ける理由は、人々は「他者が自分の話にどれほど関心を持つか」を低く見積もる傾向があると研究では予測した。
それらのことを検証するため、7つの実験を行った。
実験の結果わかったことは、「深い会話が浅い会話よりもつながりを強化し、幸福感を増すことを過小評価している」ことであった。特に「他者の関心や配慮を誤解していること(=人は深い会話を望んでいない)」が深い会話を妨げる主要な要因であると判明した。
研究者らは「深い会話に対する被験者の予想は、他者と更に深く関わらせないようにする、誤った調整がなされていた」と述べた。
とのことです。
なるほど、、、浅い会話のほうが無難でよさそうだけど、実際に蓋を空けてみるとそうでもなかった、ということですね。
「自分自身が、相手は自分と深い話をしたくないだろう」と思ってしまう誤解が心理的障壁になっていたというのは、実に興味深いところです。
■研究の概要
では、具体的にどのような研究を行ったのでしょうか。
本実験で取り扱われる「浅い会話」と「深い会話」について、どのようなものかを紹介した上で、7つの実験のポイントをまとめてみます。
(研究のまとめは7つあるので、読み飛ばしいただいて大丈夫です。ポイントは最後に改めてまとめます)
◎「浅い会話」と「深い会話」の質問
<浅い会話の質問>
浅い会話の質問は、軽いテーマや表面的なトピックに焦点を当てており、深い自己開示を求めない内容です。以下の質問が記載されています。
1.最後に1時間以上歩いたのはいつですか?どこに行き、何を見ましたか?
2.昨年のハロウィンはどのように過ごしましたか?
3.早起き派ですか、それとも夜型ですか?その理由は何ですか?
4.最近見た中で最も面白いテレビ番組は何ですか?相手に教えてください。
5.どのくらいの頻度で髪を切りますか?どこで切りますか?最悪の髪型体験をしたことはありますか?
<深い会話の質問>
深い会話の質問は、親密で個人的なテーマに焦点を当てており、被験者に自己開示を促す内容です。以下の質問が記載されています。
1.あなたの人生で最も感謝していることは何ですか?
2.もし水晶玉が未来や自分の人生について何かを教えてくれるとしたら、何を知りたいですか?
3.相手と親しい友人になるとしたら、どのようなことを知っておくべきですか?
4.他の人の前で泣いたことがある場合、それについて説明してください。
5.あなたの人生で特に恥ずかしかった瞬間を1つ教えてください。
なるほど、確かに「深い会話」のほうが、ぐっと相手の柔らかい部分に踏み込む感じがします。
では、実際に「浅い会話」と「深い会話」にまつわる実験はどのようなことが行われ、どのような発見があったのでしょうか。以下見ていきましょう。
◎実験1.深い会話が予想よりも良い経験をもたらすことの検証
<被験者>
・金融業界の役員 (1a)、金融サービス会社の管理職・従業員 (1b)、国際MBA学生 (1c)。
<方法>
・被験者は事前に、深い会話において予想される相手の関心、会話の気まずさ、つながりの強さ、幸福感を報告しました。その後、深い会話の質問(例:「あなたが人生で最も感謝していることは何ですか?」)を使用して、見知らぬ相手との10分間の対話を行い、終了後に実際の経験を報告しました。
<結果>
・深い会話は予想よりもつながりを強め、気まずさを軽減し、幸福感を向上させました。
・被験者は相手が自分の話に関心を持つ度合いを過小評価していました。
◎実験2. 浅い会話と深い会話の比較
<被験者>
修士課程の学生178名。
<方法>
被験者はランダムに浅い会話(例:「最近見たお気に入りのテレビ番組は何ですか?」)または深い会話(例:「もし水晶玉が未来を教えてくれるなら何を知りたいですか?」)のいずれかの条件に割り当てられました。会話前後で気まずさ、つながり、幸福感を評価し、さらに会話後の孤独感を測定しました。
<結果>
・深い会話は浅い会話よりもポジティブな結果をもたらし、気まずさを予想以上に軽減しました。
・被験者は深い会話の気まずさを大幅に過大評価していました。
◎実験3. 被験者自身が生成した質問を使用した会話
<被験者>
大学生と地域住民200名。
<方法>
被験者は浅い質問と深い質問を自分で生成し、ランダムにペアを組んでどちらかの質問を使用して会話しました。会話前後で期待と実際の経験を評価し、会話のポジティブさを比較しました。
<結果>
・被験者は深い会話を過度に気まずいと予想しましたが、実際には浅い会話と同程度の快適さでした。
・質問を自分で生成した場合でも期待と経験の差は同様に観察されました。
◎実験4. 他者の関心を過小評価するメカニズムの検証
<被験者>
大学生と地域住民を中心とした多様なグループ。
<方法>
被験者に浅い会話と深い会話の条件を与え、それぞれの会話で自分の発言に対する相手の関心を予測してもらいました。会話前後で気まずさ、つながり、幸福感を測定しました。
<結果>
・深い会話において、被験者は相手が自分の発言に関心を持つ度合いを過小評価しました。
・他者の関心を低く見積もることが、深い会話の気まずさを過大評価する原因となっていました。
◎実験5. 親しい相手と見知らぬ相手の比較
<被験者>
親しい友人や家族、見知らぬ相手と対話する被験者グループ。
<方法>
被験者は親しい相手または見知らぬ相手と深い質問を使用した会話を行い、会話前後で期待と実際の経験を比較しました。つながりの強さと幸福感の予測精度を測定しました。
<結果>
・親しい相手との会話では予測が正確であった一方、見知らぬ相手との場合には予測と実際の経験の間に大きなギャップが見られました。
◎実験6. 浅い会話と深い会話の両方を経験する比較実験
<被験者>
修士課程の学生や社会人グループ。
<方法>
被験者に浅い会話と深い会話の両方を経験させ、その結果を直接比較しました。気まずさ、つながり、幸福感を測定しました。
<結果>
・深い会話は浅い会話よりもつながりと幸福感を向上させましたが、期待に基づく気まずさの過大評価は継続して観察されました。
◎実験7. 誤った期待を修正する介入の効果
<被験者>
オンライン参加者を含む多様なグループ。
<方法>
被験者に他者の関心に関する情報を提供し、その情報が深い会話への心理的障壁を減少させるかを検証しました。会話前後で期待と実際の経験を評価しました。
<結果>
・他者が深い会話に高い関心を持つことを示す情報が提供された場合、被験者はより積極的に深い会話を選択しました。
・この介入により、深い会話の気まずさに対する過大評価が軽減されました。
■まとめと感想
7つの実験から、「深い会話」がもたらす幸福感やつながりの深さ、気まずさの解消などのメリットが改めて明らかになりました。
これらのことは、ある意味予測通りだったかもしれません。しかし、実験では、私達は「深い会話は気まずいと過度に思っていること」が、深い会話をするのを阻んでいることが明らかになりました。でも、実際はそうではありませんでした。(深い会話も浅い会話も気まずさは同じくらい)
また「自分の深い話を、そんなに相手は興味を持っていない」とこれも、”自分で思い込んでいること”がわかりました。しかし、実際はそうでもありませんでした。
自分の感覚ではなく、研究結果から見ると「もっと飛び込んで深い話をしてみると、得られるものがたくさんありそう」と思わせてもらえる論文であると感じさせられる内容でした。
深い話、もっとしていきたいものですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>