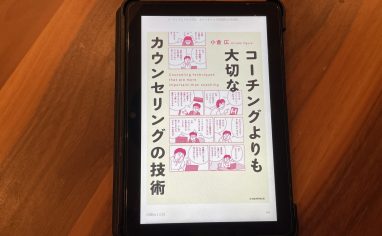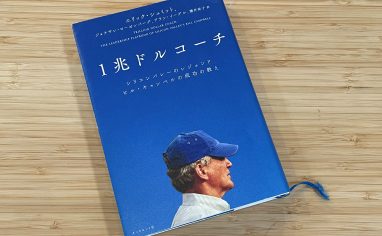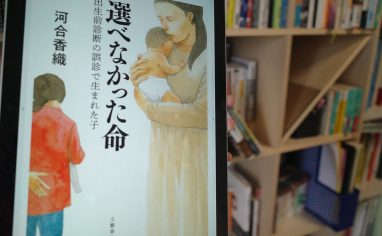生まれて初めてオーケストラを観に行って、感動した話。
(本日のお話 2654字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日金曜日は、出版に向けた資料作成、
ならびに企業研修のプログラム開発など。
*
さて、本日のお話です。
昨夜は、生まれて初めて「オーケストラ」なるものを鑑賞しにいきました。
ピアノを趣味としてやっているものの、正直オーケストラはよくわかりません。クラリネットとオーボエの違いもぱっと見同じに見える。ファゴットは動物の名前に思えます(フェレットですね)。
どの楽器がどの音なのかもよくわかりません。
オーケストラの奏でる音は嫌いではないけれども、「感動を覚える」「興奮する」といった感性を自分が持ち合わせているとも思えませんでした。
・・・ただ、若き哲学者の友人(トランペット&ピアノ奏者)と、趣味の合う年上の友人(クラシック愛好家)と3人でたまに集まって語る「通称:謎の会」というところで、「次はオーケストラでも観に行こうか」となったのでした。
そして、実際に観に行ったら「予想以上よりも、ずっとよかった」のでした。新しい趣味が増えそうで、なんだかワクワクした12月の夜。
ということで、今日はそのお話について書いてみたいと思います。
それでは、どうぞ。
■オーケストラにいろいろある(らしい)
先日集まったときに、若き哲学者のHさんと、クラシック愛好家のMさんがあれこれ語っているのを、横で聞いていました。
「やっぱり音はサントリーホールですよね」「NHKホールは大きすぎるんですよね」「ミューザ川崎もいいですよ!」などなど。私は全くわからず「そんなものなのか」と横で聞くだけになっていました。どうやらオーケストラにはいろいろ種類があり、好みも分かれるようです。
どうやらMさん的には、「サントリーホールの音が良い」のだそう。理由は、2000人という適度な収容人数に加え、コンサート用に作られているので音がよく響くところが良いとのこと。
そして初心者の私に気を遣っていただき、曲目や楽団も安定感があり退屈しないものを、ということで「NHK交響楽団」(安定した演奏で素晴らしいらしい)を選び、有名どころの曲目を検討していただきました。そして、12/6の昨日の公演に決定しました。
■AIを駆使してオーケストラについて学ぶ
当日の曲目は、以下の3つでした。
・スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲
・ラフマニノフ/ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
・ムソルグスキー(ラヴェル編)/組曲「展覧会の絵」
オーケストラは、1曲目が軽めの曲、2曲目が3部構成の協奏曲、3曲目がさまざまな楽器が加わった組曲となることが多い(らしい)です。後半に向けて、どんどん盛り上がっていく構成になっている、ということなのでしょう。
ラフマニノフとラヴェルはわかります。「展覧会の絵」は超有名で、誰もが聞いたことのある曲なので、これもわかりました。でも、曲がなんとなくわかるだけで、詳しいことは知りません。
せっかく行くのならと、それぞれの曲の背景や作曲された時期などを、生成AI(Perplexity)であれこれ調べてみました。
すると、いろいろ教えてくれました。NHK交響楽団の歴史、「展覧会の絵」の10曲の構成、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲」の特徴、そこから関連検索で出てきた「カデンツァ(ピアノのソロパート)」が見どころだという話まで。多くの情報に「へー、ほー」と感心しながら調べていました。
さらに移動中、曲目を聴きながら「実際の演奏とどう違うんだろう」とイメージを膨らませつつ、Apple Musicで予習もしました(途中からただのバックミュージックになった)。
■プロの技に震える
さて、当日サントリーホールにいくと、来場者の年齢は高め(50代後半~60歳以上が最もボリュームゾーンに見えました)でした。チケット代も高くなっているので、若い人は手が届かないという背景もあるようです。
開演の時間になると、場内が静まり返り,指揮者が前に立つと、さほど間をおかずに、演奏が始まりました。
最初の音を聞いた時、思わず息を殺して聴いていました。なんというか、言葉にする味気なくなりそうなのですが、「プロってすごい……」と、ただただ思うばかりでした。
当たり前かもしれませんが、オーケストラの曲を何人ものヴァイオリン奏者が、一糸乱れず奏でていく。その音を安定して鳴らすだけでもアマチュアには超高難度。そんな技術を、人生を懸けて磨き上げた奏者たちが、一つの音楽を作り上げている。
音楽に詳しいHさんは「N響に入ることは、東大に入るよりずっと難しいんですよ。株主総会の集まりよりもずっとすごいw」と言っていましたが、なんだか納得してしまいました。
磨かれた腕が集まり、一つの曲を奏でることを生で聴くこと。それは相応に歳を重ねたゆえに、物語や重みを覚え、価値を感じるのかもしれません。
加えて、目で見ながら音を聞くと、「ああ、ここの主旋律はこの人が吹いているんだ。このタイミングで旋律がバトンを渡されていくんだ」とか、「この二つの楽器が合わさってこういう音になるんだ」、と素人ながらも生の演奏を「観る」からこその気づきもあり、非常に豊かな時間でした。
「やっぱり、”生で観る”ことがないと、どの楽器が、どういう音なのかもわかりませんよね」とMさんは言っていましたが、まさにその通りだと思いました。
■まとめ:音楽は儲からないけれど
クラシックの業界で働く私のピアノの先生曰く、「音楽、特にクラシック業界はお金にならない、ビジネスとしてやっていくのは難しい」とのことでした。そもそも聴く人が限定されているし、新しく興味を持つ人も少なくなっている、と。
膨大な練習を経ても、音楽はもともとパトロンのような人がお金を出して支えてきた歴史もあります。そのため、業界の特性上,それ単体でお金が動くことが少ないのは宿命なのかもしれません。
でも「儲かる儲からない」に関係なく、そうした洗練された技術は、多くの人の心を揺さぶる価値があります。
私も趣味でピアノを弾いていますが、さして上手くこのピアノが、一体何の役に立つのか?と言われたら、特に自分以外は役に立っていないとしか言いようがありません。
「働き盛り、社会のためにもっとやるべきことがあるんじゃないの?」と言われたら、それまでかもしれません。
でも、こうした「感性を揺さぶる遊び」があるから、人生が明るく感じられるし、毎日が楽しくもなると思いますし、自分にエネルギーが補充される感じられます。
改めて,「無用の用」という言葉を思い出しつつ、良い時間だったなあ,と感じた次第です。もしご興味がある方は、ぜひ。きっと良い時間になるかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>