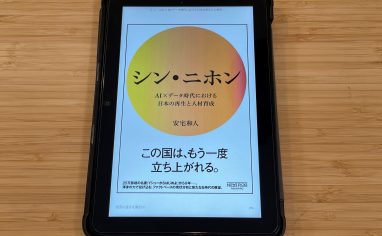知恵を高める7つの方法 ー「ベルリン英知パラダイム」からの知見ー
(本日のお話 3445字/読了時間6分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、2件のアポイント。
その他、研修の準備や、論文の調査などでした。
*
さて、本日のお話です。
出版企画に向けて(まだ出せるかもわかりませんが)、引き続き「性格の強み」に関連する論文を集めている今日この頃です。
さて、本日は性格の強みの「大局観」にも関わる概念である『英知・知恵(Wisdom)』についての学びを紹介させていただきます。(以下、「Wisdom=知恵」に統一します)
今回ご紹介する論文は、「知恵(Wisdom)」を科学的・心理学的に紐解いた初めての論文です(引用数も2413となかなか多い)。
本論文では、「知恵の構成要素」を明らかにし、また「効果的に知恵を高める方法」を整理しています。簡単に言えば「賢い人になれる道筋を示してくれた」ような、そんな素敵な論文でございました。
ということで、早速まいりましょう!
=============================
<今回の論文>
タイトル:Wisdom: A Metaheuristic (Pragmatic) to Orchestrate Mind and Virtue Toward Excellence
英知:卓越性へ向けた心と徳を調和させるメタヒューリスティック(実用的指針)
著者:Paul B. Baltes, Ursula M. Staudinger
ジャーナル:American Psychologist, 2000年
=============================
■1分でわかる本論文のポイント
・本論文は、これまで研究では哲学や宗教に限定されていた「知恵(Wisdom)」について、”科学的・心理学的”に解明し、その発達や応用可能性を探りました。
・まず、知恵を「人生の設計、管理、振り返り」に関する深い専門知識と定義しました。
・そして知恵の評価には「ベルリン英知パラダイム」という実証的アプローチを使用しました。これは、知恵を5つの要素からなると考えます。
・研究の結果(533名の成人を対象にした研究)では、知恵は年齢や人生経験と深く関連していること、特に25〜75歳で安定して発揮されることが分かりました。
・また、知恵を高める効果的な方法として、「対話」「メンターシップ」「ライフスパン文脈の理解」「多文化理解」「実践的課題への取り組み」などが特定されました。
とのことです。
ポイントは「ベルリン英知パラダイム」という考え方、そして、「知恵を高めるための方法論」に触れられているところです。
■「ベルリン英知パラダイム」とは
さて、本論文の一番のポイント「ベルリン英知パラダイム」(Berlin Wisdom Paradigm) ですが、これは知恵(Wisdom)を心理学的に研究・測定するために、Paul B. Baltes らが開発した理論的枠組み、および評価方法です。
こちらが開発される1990年代までは、哲学や宗教でしか研究されてこなかった「知恵」という考え方が、科学的・心理学的に考えることができる起点となった論文でした。
まず、「知恵の定義」ですが、以下のように示されました。
――――――――――――――――――――――――――――――――
【「知恵(Wisdom)」の定義】
「人生の計画、管理、振り返りに関わる知識と判断力の卓越した体系であり、個人および社会の幸福を追求するもの」。
――――――――――――――――――――――――――――――――
そして、「知恵を構成する5つの基準」として以下「ベルリン英知パラダイム」が開発されました。言い換えるならば、「賢人の5つの要素」とも表現できるかと思います。
(ここから)
――――――――――――――――――――――――――――――――
【ベルリン英知パラダイム ~知恵を構成する5つの基準~】
(1)事実的知識(Factual Knowledge)
人生の基本的な事実や本質に関する深い理解。
(例:人間の発達、社会的関係、文化的多様性に関する知識)
(2)手続き的知識(Procedural Knowledge)
問題解決や意思決定を行うための実践的な戦略。
(例:複雑な課題や対立する価値観への対応方法)
(3)ライフスパン文脈主義(Lifespan Contextualism)
人生の異なる文脈(個人的、社会的、文化的)や時間的視点(過去、現在、未来)を考慮する能力。
(例:人生の目標や選択肢を歴史的・社会的背景の中で捉える力)
(4)価値相対主義(Value Relativism)
異なる価値観や目標を尊重し、調和させる能力。
(例:多様な文化や信念の違いを認識し、公平に評価する力)
(5)不確実性の認識と管理(Uncertainty Awareness and Management)
予測不可能性や知識の限界を認識し、それに柔軟に対応する力。
(例:複雑であいまいな状況への適応力)
――――――――――――――――――――――――――――――――
(ここまで)
■研究の概要
では、このような「ベルリン英知パラダイム」を含めて、実際にどのような研究がされたのでしょうか? 以下、研究の背景・方法についてまとめます。
◎研究の背景
・知恵は古代ギリシャの哲学や宗教で「善良で意味のある人生」の指針として研究され、ソクラテスやアリストテレスがその基礎を築きました。
・20世紀に入り心理学でも議論され、エリクソンやSternbergが知恵を認知的発達や自己統合と関連付けました。
・しかし、科学的に測定可能なモデルは不足しており、本研究では知恵を「人生の実践的知識」として定義し、実証的評価を試みることにしました。
◎研究の方法
1.参加者
研究対象は20〜89歳の成人533名で、年齢、教育水準、社会的背景が多様な集団から選ばれました。
2.思考プロトコルの収集
参加者には架空の生活課題が提示され、これに対する思考プロセスを「考えながら声に出す」方法で記録しました。例として以下のような課題が提示されました
<課題の例>
・課題1: 親しい友人が自殺を決意した場合、どのように対応すべきか?
・課題2: 15歳の少女がすぐに結婚を望んでいる場合、どのような助言を行うべきか?
3.評価基準
回答は以下の「ベルリン英知パラダイム」の5つの基準で(事実的知識、手続き的知識、価値観の多様性の理解、ライフスパン視点、不確実性への対応力)で評価しました。
評価は7段階スケールで行われ、評価者間の一致率が高い(r = .65〜.94)信頼性のあるスコアリングが実施されました。
■結果わかったこと
以下、研究の結果、わかったことについて記述します。
●わかったこと1: 「年齢と知恵の関係」について
・知恵スコアは、25〜75歳の間で大きな変化はありませんでした。
・主な知恵の獲得は15〜25歳に集中しており、75歳以降ではわずかな低下が見られました。
●わかったこと2:「対話」が知恵を高める
「他者との対話」や「内的対話」を通じて知恵スコアが平均で1標準偏差向上しました。
●わかったこと3:「職業経験の影響」がある
臨床心理学者は、他の職業群と比較して高い知恵スコアを示しましたが、専門的基準で「エキスパート」レベルには達していませんでした(平均スコア3.8/7)。
また、成人の知恵に影響を与えるモデルが示されていました。
■「知恵」を高める7つの方法
以下、7つの効果的な知恵の高め方について、紹介いたします。
(ここから)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<知恵を高める7つの方法>
1.みんなと話し合って考えよう(対話の活用)
対話や内的な話し合いで、新しい考え方を見つけて英知を深めます。
2.経験豊かな人から学ぼう(メンターシップの活用)
メンターや指導者に教わりながら、価値観や判断力を高めます。
3.長い人生の視点を持とう(ライフスパン文脈主義の強化)
人生の過去・現在・未来をつなげて、物事を広く考える力を養います。
4.ことわざで知恵を学ぼう(文化的知識の活用)
格言やことわざを使って、人生の問題を解決する方法を見つけます。
5.新しいアイデアを作ろう(創造性と批判的思考の育成)
創造力や批判的思考を使って、難しい問題に挑みます。
6.現実の問題に挑戦しよう(実践的課題解決の実施)
実際の課題を解決する練習をして、役立つ知識を身につけます。
7.違う文化や考えを知ろう(価値相対主義と多様性理解)
他の文化や考え方を学び、多様な視点を取り入れる力を育てます。
※ChatGPTにて要約・編集
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(ここまで)
■まとめと感想
「知恵がある人って、聡明でカッコいいなあ」となんとなく思っていましたが、その構成要素が5つに分けられることで、「賢人の5つの要素」(事実的知識、手続き的知識、価値観の多様性の理解、ライフスパン視点、不確実性への対応力)が明確になったように思いました。
また、その上で、どうすれば「知恵」を鍛えられるかについても効果的な方法が示唆されていたところも興味深く思いました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>