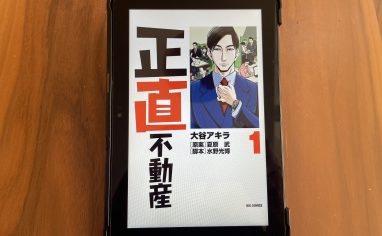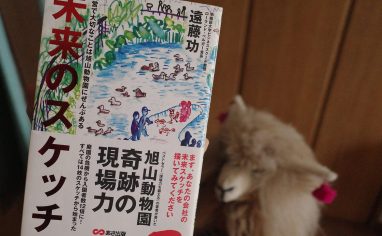「勇気の筋肉」の鍛え方 ~論文『職場における勇気』より~
(本日のお話 3432字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
さて、本日も論文のご紹介をさせていただきます。
今日のお話は「勇気」についてのお話です。
今日のテーマは「職場における勇気(Workplace Courage)」を題材にした論文です。
(そもそも、勇気というテーマの論文があるんだ・・・!と驚きでした)
・そもそも「勇気」とは何か?
・職場において「勇気」が必要な場面とは?
・そして、「勇気」を持つためにどんなことができるのか?
そんなことをレビュー論文として、過去の研究をまとめた興味深い内容でした。
ということで、早速まいりましょう!
――――――――――――――――――――――
<目次>
今回の論文
1分でわかる本論文のポイント
研究の方法
結果:わかったこと
(1)「勇気」には3種類ある
(2)「職場における勇気」の定義
(3)「職場における勇気」に関連する理論
「勇気の筋肉」を鍛える方法
(1)暴露療法
(2)認知行動療法(CBT)
――――――――――――――――――――――
=======================
<今回の論文>
タイトル:Workplace Courage: Review, Synthesis, and Future Agenda for a Complex Construct(職場における勇気:レビュー、統合、そして複雑な構造に関する今後の課題)
著者:James R. Detert, Evan A. Bruno
ジャーナル:The Academy of Management Annals, 2017年
=======================
■1分でわかる本論文のポイント
・本論文は、「職場の勇気」というテーマについて、既存の文献を整理し、統合し、批判的に検討することを目的とした。
・勇気という概念は、古代哲学者のプラトンやアリストテレスの時代から始まり、近代においては心理学や組織行動学の分野でも勇気に対する関心が高まり、長きに亘って議論されてきた。
・しかし、職場における勇気については、適切な定義や測定方法が欠如しており、研究が散在しており、また職場における適用に関する研究は極めて限られている。
・本論文は、これらのギャップを埋めるために、職場の勇気に関する文献を包括的にレビューし、その基盤を構築することを目指した。
という内容です。
後ほどご紹介しますが、「勇気の種類」や「職場における勇気に似た概念」なども整理されており、なるほどなあ、と興味深く、勉強になりました。
より詳しく見ていきたいと思います。
■研究の方法
本論文はどのように調査が進んでいったのでしょうか。
まず、研究の方法は、以下のようなプロセスで行いました。
・理論的・実証的に関連性の高い約100件の文献を体系的にレビューした。
・レビューした論文のカテゴリは「勇気に関する歴史的・哲学的な議論」から「最新の組織科学的研究」まで、幅広くカバーをし、調査した。
・上記の結果、「職場における勇気の行動的特徴」「理論的課題」「測定方法のレビュー」等を通じて包括的な議論を行った。
とのことです。
■結果:わかったこと
そして、研究の結果わかったこととして、以下のような点が述べられていました。
◎(1)「勇気」には3種類ある
勇気に関連する文献を整理したところ、以下の3つの主要な行動カテゴリーが特性されました。
1.命や身体を危険にさらす行動(例:消防士の任務)。
2.現状に挑戦する行動(例:上司への異議申し立て)。
3.心理的挑戦を伴う行動(例:自己改善を目指す行動)。
◎(2)「職場における勇気」の定義
本論文のレビューと評価を通じ「職場における勇気」について、以下3つの要素が含まれる中で行動することと、研究者らは考えました。
(ここから)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<職場における勇気の「要素」>
1.リスク: 身体的、心理的、経済的、社会的リスクを含む。
2.価値: 社会的または道徳的に意義のある目的に向けた行動。
3.職場関連性: 行動が職場環境や関係者に直接的または間接的に関連していること。
<職場における勇気の「定義」>
「重大なリスクがある状況下で、行為者が価値のある目的のために意図的に行う、職場関連の行動」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(ここまで)
勇気とは「リスク」「価値」「職場に関連」したものを含むということですね。
確かに考えてみれば「不正の内部告発」「上司(権威者)へのフィードバック」「現状維持ではなく改善の声を挙げる」など考えてみると、どれも上記3つの要素を含みます。
声を挙げるとは、”干される”とか”復讐される”とか、そうしたリスクを伴う行動だということも同時によくわかります。。。
◎(3)「職場における勇気」に関連する理論
そして、これらの「職場における勇気」と、概念的・理論的に重複する内容がまとめられていました。ここでは6つの論文から、重複概念が紹介されています。以下、ご紹介いたします。
(ここから)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1)積極的・建設的逸脱(Positive or Constructive Deviance)
規範を意図的に逸脱しつつも、建設的で肯定的な目的を持つ行動。
例: 規則を破るが、組織全体の利益を促進する行動。
2)内部告発(Whistleblowing)
不正や違法行為を明るみに出すためのリスクを伴う行動。
例: 法律違反や倫理違反を公表する従業員。
3)積極的行動(Proactive Behavior)
環境や自己にポジティブな変化をもたらすための先を見越した行動。
例: 職場のプロセス改善を目的とした自発的な提案。
4)援助行動(Helping)
他者を支援するために行われる自己犠牲を伴う配慮深い行動。
例: 困難な状況にある同僚を助ける行動。
5)改善志向の意見表明(Improvement-Oriented Voice)
現状に満足せず、建設的な意見を表明し、状況を改善する行動。
例: 非効率的な慣習を指摘し、改善案を提案する行動。
6)社会的利益を目的とした規則破り(Prosocial Rule Breaking)
他者や組織の利益のために、意図的に規則を破る行動。
例: 顧客満足のために厳格な規則を柔軟に扱う行動。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■「勇気の筋肉」を鍛える方法
さて、論文の後半では「勇気を育んだり、刺激したりする方法」について、述べられています。実際に、レビューした論文の4分の3以上が何かしらの介入策を提案しています。ただ、簡単なアイデアにとどまっているため、今回の論文では「理論をもとにした介入方法を提案」すると述べています。
紹介されていたものは、以下の2点でした。
◎(1)暴露療法
恐怖反応を緩和し、望ましい行動を増やすためのクラシックなアプローチ。
ステップとしては、以下のようなアプローチがあります。
<アプローチ1:段階的に恐怖に慣れていく>
1.個人が恐れている状況(例:公の場で意見を述べる)に段階的に慣れる機会を提供する
2.恐怖心を徐々に克服し、最終的には対象となる行動に自信を持てるようにする
(例: 最初は1対1で意見を述べる練習を行い、最終的にはグループで意見を述べる、など)
<アプローチ2:感情的な負担を軽減する>
1.恐怖心や不安感を緩和するため、行動に対する肯定的なフィードバックや支援を提供する。
2.安全で支援的な環境を用意して、不安が低減した状態で行動を試みる。
(例: 最初に親しい同僚の前で練習し、その後徐々にリスクの高い場面へ移行する)
◎(2)認知行動療法(CBT)
またもう1つの、認知行動療法は、勇気を育成する方法として提案されています(Pury, 2008; Steinfeldt, 2015)。たとえば、以下のようなステップを踏みます。
1.認知の特定と修正
否定的な思考(例:「失敗したら笑われる」)を認識し、現実的でポジティブな考えに置き換える。(例: 「失敗しても学べる経験になる」と考え直す)
2.現実的な考え方の強化
誤った思考パターンを修正し、行動の価値や可能性を現実的に評価する訓練を行う。(例: 「完璧ではなくても、提案するだけで価値がある」と自分を評価する)
3.安全な環境でのスキル練習
ロールプレイやシミュレーションを通じて、勇気ある行動を実践的に練習する。(例: 上司に提案を伝える場面を想定したロールプレイを行う)
■まとめと感想
個人的な話ですが、私の会社は「カレッジ(Courage)」と、まさに「勇気」としています。
今回の論文でいえば、勇気の行動のうち、「心理的挑戦を伴う行動(例:自己改善を目指す行動)」を意味して名付けました。
誰もが「新しい一歩を踏み出す」というのはドキドキします。
でも、「勇気」を持って一歩踏み出すと、そこから色々と新しい可能性が拓けていき、一人ひとりがよりハッピーになっていけるの・・・と私は思っています。そんな「勇気ある小さな一歩」を応援したいと思い、「カレッジ」という社名にしました。
そんな「Courege」という概念について、より詳しく理解できた論文であり、大変興味深く思った次第です。
最近はウルトラマラソンで身体的な痛みを伴う勇気ばかり使っている気がしますが(笑)、私が苦手な対人面における「勇気」も大切にしたいと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>