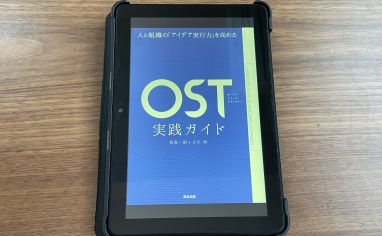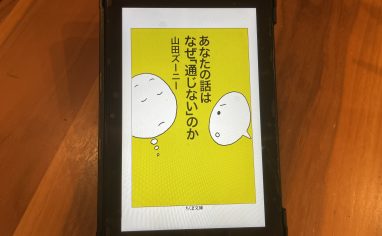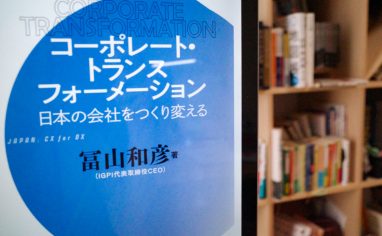「ビックファイブの理論と歴史」を論文から紐解く
(本日のお話 3515文字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は2件のアポイント。
また10kmのランニングでした。
その他、粛々と進めている出版企画の作成など。
さて、本日のお話です。
本日は「性格モデル」についての論文をご紹介いたします。
心理学の性格モデルに「ビックファイブ」と呼ばれる有名なものがあります。
以前から知ってはいましたが、このビックファイブに直接関わる論文を、これまで読んだことがありませんでした。
本日はこの「ビックファイブ」に関する論文の中で、引用数15969(25.1.8時点)の著名な論文をご紹介したいと思います。
読みながら、「性格の分類って、こんな研究者たちの血と汗と涙の結晶で出来上がってきたんだ・・・!(遠い目)」と研究の軌跡に知的興奮を覚えた論文でした。
ということで、早速見てまいりましょう!
==============================
<今回の論文>
タイトル:『Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives』(ビッグファイブ特性分類法:歴史、測定、理論的視点)
著書:Oliver P. John, Sanjay Srivastava
ジャーナル:Personality Handbook, 2nd Edition
パーソナリティ・ハンドブック 第2版(1995年)
==============================
■ビックファイブとはなにか
さて、そもそも「ビックファイブ」とは、ビッグファイブは、人間の性格を5つの主要な特性で説明する心理学的モデルです。
・外向性 (Extraversion):社交性、エネルギッシュさ、感情の表現。
・協調性 (Agreeableness):他者への信頼、利他主義、寛容性。
・誠実性 (Conscientiousness):自己規律、秩序、達成志向。
・神経症的傾向 (Neuroticism):不安、抑うつ、感情の不安定さ。
・開放性 (Openness to Experience):想像力、創造性、価値観の柔軟性。
異なる文化と言語においても、ビックファイブ構造が再現されることが確認されています。かつ上記の「各特性は独立しており、正規分布を形成する」こともわかっているそうです。(つまり、多くの人々は各特性において中程度の値を示し、極端な値を示す人は少ないということ)
ビックファイブと各指標(年収や健康など)との相関を示す研究も多くなされている、有名なモデルとして知られています。
※ビックファイブの簡易的なテストはこちらから受検可能です。
↓↓
https://big5-basic.com/front/index.php?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvvO7BhC-ARIsAGFyToXr0R8Au8ik6zHfVScvkDg0xpaoJhIlr8z0TXa-iN9m6XVY8Cry0xsaArP2EALw_wcB#google_vignette
■ビックファイブの歴史
いつからか知られるようになったこのモデルですが、ではいつから研究が始まったのでしょうか? 今回紹介の論文ではその歴史を含めて説明されていました。以下3つの観点から解説をいたします。
1)パーソナリティ研究の課題
・性格特性を測定する尺度が非常に多様で、研究者間の共通言語が不足していました。そして、性格特性間の概念の重複や命名の不統一が、知見の統合を阻んでいることが、パーソナリティ(性格)の研究の課題でした
2)語彙仮説
・前提として「性格の特徴は言葉に現れている」と仮定しました(語彙仮説といいます)。つまり、”優しい”とか”粘り強い”などです。
・これを辞書から抽出した性格関連用語の因子分析に基づき、分類法を作成しました。(たとえば、状態=一時的なもの、性格特性=安定した長期的なもの、というような分け方など)
3) ビッグファイブの発展
・上記のような課題と語彙仮説などから、1930年代から研究が始まります。
・初期の研究(Allport & Odbert, 1936)では、膨大な性格記述用語を分類しました。当初は「18000語」もの性格を表す言葉があったそうです。「悪夢のよう」「(まとめるために)生涯働くことになるだろう」と研究者は述べていたという記録があります。
・Cattell(1943)は、用語を要約し、因子分析に基づく12の性格次元を抽出しました。そして、Fiske(1949)やTupes & Christal(1961)らが、主要な5因子を発見し、今のビックファイブの源流となります。
・そしてGoldberg (1981)が「ビッグファイブ」という呼称を提案し、5因子構造の理論的枠組みを整理し、発展を重ね、今に至ります。
■ビックファイブの5つの特性の詳しい解説
では、それぞれの特性は具体的にどのような意味を持つのでしょうか? 以下、論文以外も含めてですが、獲得性の定義との下位因子の例をまとめてみます。
◎外向性 (Extraversion)
外向性は、社交的で積極的な行動傾向を反映します。この次元に高い人は、他者との交流を好み、エネルギッシュで陽気な性格を持つ傾向があります。低い人は内向的で、静かに一人で過ごす時間を好むことが多いです。
<特徴的な要素>
・積極性:周囲との積極的な関わりを持つ。
・社交性:大人数の中でも快適に過ごす能力。
・感情表現:感情を豊かに表現しやすい。
・冒険性:新しい経験や活動を追求する姿勢 など
◎協調性 (Agreeableness)
協調性は、他者と友好的で思いやりのある関係を築く能力や傾向を表します。この次元に高い人は、共感的で、他者のニーズを優先することが多いです。一方で低い人は競争的で、批判的な行動をとることがあります。
<特徴的な要素>
・信頼:他者を疑うことなく信じる態度。
・利他主義:他者の利益を優先する姿勢。
・順応性:意見の違いに寛容で、対立を避ける傾向。
・謙虚さ:自己主張を控え、控えめな態度を取る。 など
◎誠実性 (Conscientiousness)
誠実性(勤勉性)は、目標達成のために計画的で責任感のある行動を取る傾向を表します。この次元に高い人は、自己管理能力が高く、慎重で信頼性があります。低い人は、衝動的で計画性に欠けることがあります。
<特徴的な要素>
・自己規律:タスクを最後までやり遂げる能力。
・秩序:物事を整理整頓し、計画的に進める姿勢。
・目標志向:達成したい目標に向かって努力する意志。
・慎重さ:決定を下す前に十分に考慮する態度。 など
◎神経症的傾向 (Neuroticism)
神経症的傾向は、感情的な安定性やストレスに対する反応性を示します。この次元に高い人は、不安や怒り、抑うつを感じやすく、ストレス耐性が低い傾向があります。低い人は、冷静でストレスに強い性格です。
<特徴的な要素>
・不安:未来や失敗に対する過度の心配。
・怒り:苛立ちや攻撃的な感情を持ちやすい。
・抑うつ:悲しみや落ち込みを感じやすい。
・情緒不安定:気分が変わりやすく、コントロールが難しい。 など
◎開放性 (Openness to Experience)
開放性は、新しい経験やアイデア、価値観に対する受容性や創造性を表します。この次元に高い人は、好奇心が旺盛で想像力が豊かです。低い人は、現実的で伝統的な考え方を好む傾向があります。
<特徴的な要素>
・好奇心:新しいことを学びたいという強い欲求。
・創造性:新しいアイデアや方法を生み出す能力。
・審美眼:美しいものや芸術に対する感受性。
・柔軟性:異なる視点や意見を受け入れる態度。など
■まとめと感想
「ビックファイブ」が1930年代から始まっていたこと、18000語もの性格を表す言葉から語彙仮説なるものから絞られていったことなどの、研究者たちの涙ぐましい努力のもとに形づくられていった歴史に、凄みを感じました。
またビックファイブは「正規分布を示す」「文化間でも信頼性が高い」なども示されており、やはり有名になった理由もわかるように思いましたし、軸となる研究には、多くの検証がされているのだと学びになりました。
現在は、HEXACOなどより発展された性格モデルが開発されていますし、性格の強みである「VIA」との相関も示されている研究もあるので、またそちらも紹介させていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>