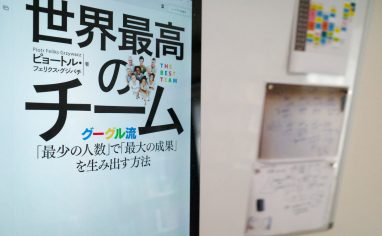おすすめの一冊『小・中・高の先生に読んでほしい探究学習の授業』
(本日のお話 2412文字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
引き続き、沖縄に来ております。
沖縄は先週は今年一番の寒波、週末は雨でございましたが(笑)、
気温はぐっと上がって、沖縄っぽさを感じております。
もう数日、沖縄リモートワークを味わいたいと思います。
*
さて、本日のお話です。
毎週日曜日は最近読んだ本をご紹介する「おすすめの一冊」のコーナーです。今週の一冊は、こちらです。
========================
<おすすめの一冊>
『小・中・高の先生に読んでほしい探究学習の授業』
森 祐介 (著)
========================
個人的な話ではありますが、著者の森さんは大学院の修士課程で共に学んだ仲間であり、100kmマラソンを共に駆け抜けた戦友でもあり、また大学院の博士課程で研究を進めている先輩のような存在です。
彼は、武蔵野学院大学や國學院大學で「探究学習」を軸にした授業を行っています。そして、この「探究学習」を活用すると、生徒の課題解決能力が高まる、創造性が高まる、ウェルビーイング(幸福度)が高まる、おまけに先生方も実はラクになる、などがわかっており、いいことが盛りだくさんの注目の学習方法です。
では、この「探究学習」とは一体何なのか?
この探究学習の考え方や事例を端的にまとめている入門書が本書です。
ということで、早速見てまいりましょう。
■「探究学習」ってなんだ?
そもそも「探究学習」なんて初めて聞いたんですけど・・・という方がほとんどかと思います。なんとなく字面でイメージはつくけど、はて、どういうものでしょうか?
本書では、以下のように説明されています。
―――――――――――――――――――――――――――――
「探究学習」とは、子どもたちが身の回りや社会の中から自ら課題を発見し、その解決に向けて横断的・総合的に学ぶ学習法です。
―――――――――――――――――――――――――――――
とのこと。
「身の回りから自ら課題を発見する」「その解決に向けて横断的・総合的に学ぶ」・・・、ちょっとまだ分かりづらいでしょうか。
もう少し具体的に見てみると、本書では、大学生が「狭山市の特産品を使ったお菓子の企画&販売をする」というプロジェクト(=探究学習)を行ったことが紹介されています。
大学生がチームになる。そして「お菓子の企画&販売をする」プロジェクトを完遂するミッションを与えられる。すると、当然、様々なことを調べたり、話し合ったり、実行する必要が出てきます。
すると、チームで役割分担をしたり、チームを巻き込むためにリーダーシップを発揮したり、企画書の作り方を覚えたり、プレゼンを練習したり・・・と、「横断的・総合的に学ぶ」ことになるわけです。これが「探究学習」の面白さです。
▽▽▽
余談ですが、私も立教大学のビジネス・リーダーシップ・プログラムの兼任講師(プロジェクト型の探究学習の授業)に携わっていますが、学生さんの成長をめちゃくちゃ感じます・・・!
本書では、探究学習の可能性について、このように述べています。
――――――――――――――――――――――――――――――――
絶対的な答えがない問題がない増え続ける時代では、ただ覚えるだけの勉強が必ずしも役に立つとは限りません。こうした時代において、子どもたちの生きる力を高め、将来の可能性を広げるために、探究学習は欠かせない学習法だという認識が広がりつつあります。
――――――――――――――――――――――――――――――――
実際に、就職面接の際に学生に求める能力は「読み書き算盤(認知能力)」以上に「コミュニケーション力やチームワーク(非認知能力)」等と言われますが、探究学習はそうした非認知能力も高めることができるそうです。
■「探究学習」で押さえたいキーワード
では、どのように探究学習を進めればよいのでしょうか。
その際に、押さえておきたいキーワードが2つあります。
「探究学習の舞台」をつくるために、関わる教育者が持っておくべき教育ポリシー、とでも言い換えられるものです。
その1:子どもたちの「エージェンシー」を育てる
エージェンシーとは「変化を起こすために自分で目標を設定し、振り返り、責任を持って行動する能力」とされます。探究学習は、子どもたちのこうした“エージェンシー”を育むという狙いがあるようです。
その2:大人たちが「共同エージェンシー」として支援する
共同エージェンシー「教えたり学んだりする過程で、親や教師、コミュニティ、子どもたちが相互に支援し合う関係性」とされます。つまり、周りの大人たちが子どもたちのエージェンシーを発揮できる舞台を一緒に作りましょう、ということです。
▽▽▽
もし、探究学習を設計する運営側にこうした「エージェンシー」や「共同エージェンシー」という考え方がなければどうなるのか。
すると先生や大人が「企画はこっちのほうがいいでしょ!」「もっとこうした方がいいんじゃない?」「進捗遅れているけど、大丈夫??」と、子どもが自主的に目標を設定する、責任を持つ存在とみなしていないような発言が生まれてしまうかもしれません。
すると、結果的に子どもたちの学習を阻害してしまうことにもなりかねない、となります。
子どもの主体性を育む関わり方を「エージェンシー」と「共同エージェンシー」という関わりに徹することが大事なのですね。
■まとめと感想
本書で語られている「探究学習」は、学校教育で注目されている考え方です。ただ、これは家庭でも同じことが言えるのでは・・・と思いました。
子どもが自分で目標を決め、そして振り返り、責任を持つ存在として接すること(子どものエージェンシーを育てる)。
そして大人は、それを支援する存在と考えること(共同エージェンシーと考える)。そうすることで、子どもの可能性の種も、より花開くように思えた次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>