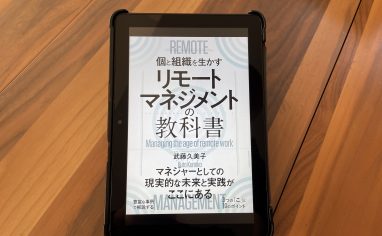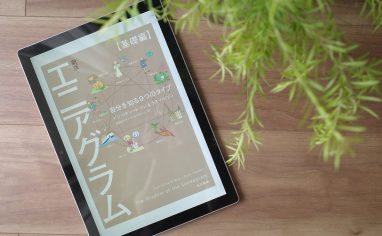「一行日記」が上達を加速させる ー経験学習モデルを活かしたピアノの練習法ー
(本日のお話 2523文字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は午前1件のアポイント。
また管理職のフィードバックに関するオンラインセミナーの実施でした。
午後からは、外部顧問として関わらせていただいている企業の
人事の方のコーチング&コンサルティングなど。
夜は、経営者仲間との懇親会でした。
*
さて、本日のお話です。
本日は土曜日とのことで、個人的に取り組んでいるピアノのお話を書いてみたいと思います。
先日、仕事終わりのピアノのレッスンの際のお話ですが、ピアノの先生が、音大の試験の伴奏の仕事をしているとの話から、音大生について、こんな話を聞かせてくれました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「音大っていっても、本当にいろんな学校があって、正直受ければ誰でも入れる、みたいなところもあるんですよね。
その中で、正直そのレベルに驚くこともあります。そもそも練習していないとか、完全に崩壊しているなど。。。でも、多分それって『練習の仕方を知らない』からなんだと思うんですよね」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
とのこと。
練習がたりない(練習の量)のはもとより、漫然と繰り返すだけでは上手くならない(練習の質)というのは、音大生であろうと、雲泥の差があるようです。
今日はこんな「上達する練習の仕方」について、学習理論を含めつつ、気づいたことをお伝えさせていただければと思います。
それでは、どうぞ!
■社会人は「練習がうまい」?
ちょっとだけ、嬉しかったことがありました。
それが、現在取り組んでいる4月の発表会の曲について弾いた時に、先生から「いい感じで上達してますね」「技術も上がっていますよ」と褒めていただいたこと。
曲と呼ぶには程遠い完成度ですが、それでも一歩ずつ進んでいることに、成長の喜びを感じます。そして、先生はこんな話もしてくれました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「社会人で時間がなくても、練習の仕方でうまくなりますね。
大人になって、練習を工夫することで上達できる人もいれば、
学生でも、練習の仕方がわからず伸び悩む人もいます」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
たしかに、私は特に社会人になって、そして特に「大学院で学んでから、ピアノの上達スピードが早まった」と感じています。
なんじゃそりゃ?、という話ですが、結論を言うと「上達につながる理論を学んだ」からです。
■経験学習が、成長を加速させる
私は4年前に、人づくり・組織づくりを学ぶ大学院に入学し、その中であることを学びました。それが『経験学習』というものです。
教科書や人から学ぶのは3割くらいしかなく、大人の学びの7割は経験であるいうこと、そして、人は「経験を振り返って、教訓にすることで成長していく」。これが「経験学習」の考え方です。
これは、デイビット・コルブの『経験学習モデル』として知られています。
以下、簡単に解説いたします。
(ここから)
―――――――――――――――――――――――――――――
<経験学習モデルとは?>
以下4つのサイクルによる「経験を振り返り、教訓化する学習モデル」。
(1)具体的経験(Concrete Experience)
具体的な経験をすること。ちなみに経験とは「本人が環境(他者やモノ)に働きかけることで起こる相互作用」のこととされる。
(2)内省的観察(Reflective Observation)
経験を振り返り、出来事の意味や自身の反応について深く考えること。
内省、省察、リフレクション、反省的思考とも言われる。
(3)抽象的概念化(Abstract Conceptualization)
内省から得た気づきを理論や一般的な原則に結びつけ、概念化する段階。
他の状況でも応用可能な知識、ルール、ルーチンなどを自ら作り上げる。
(4)能動的実験(Active Experimentation)
概念化した学びを実際の行動に応用し、新たな経験を試すこと。
そのアクションにより、また新たな経験や内省が生まれていく。
※参考:中原淳. 2013. “経験学習の理論的系譜と研究動向.” 日本労働研究雑誌 55 (10): 4–14.
―――――――――――――――――――――――――――――
(ここまで)
経験を教訓にすれば、「二度あることを、三度起こさない」(ミスなど)にも繋がりますし、「上手くいったことを言語化し、再現性を持たせる」こともできるようになります。
そしてこれは、仕事の世界はもとより、スポーツの世界でも同様です。
(ここから)
―――――――――――――――――――――――――――――
ビジネスパーソンだけでなく、一流のアスリートも経験学習を能力向上のためのベースとして活用している。北京五輪スピードスケート金メダリストの高木美帆選手は、以下のように語っている。
「練習後、部屋でひとりきりになってスケートに向き合う時間をつくり、気になったポイントをノートに書き留めるのが日課になっている。毎日似たようなことをやっていますから、気づいた点は書いておかないとどんどん忘れる。スキル的なポイントだけではなく、練習がきつくなってきたら、どういうメンタルで臨むと乗り越えられるかもメモします」(TARZAN 2018 7月12号より引用)
このように、高木選手は、練習の経験を言語化することにより経験をリフレクションしている。
永田 正樹(2024)『管理者コーチング論:上司と部下の幸せな関係づくりのために』.ダイヤモンド社 P10
―――――――――――――――――――――――――――――
(ここまで)
とのこと。まさにこれです。これが仕事だけではなく、ピアノの練習にも繋がったのでした。
■「一行日記」がピアノの上達につながった
さて、経験学習の話を、ピアノの話につなげると、「練習の質」が変わります。私はある工夫を始めてから、上達の実感を強く感じるようになったことがあります。それが「一行日記」という学習方法です。
<ピアノ練習の一行日記>
1)練習をした時間をGoogleカレンダーに入力する
2)どんな練習を行ったのかを「1行日記」として記録する
これだけです。たとえば、先週の私の例だとこんな感じでした。
私の場合は、発表会の曲を「起承転結」の部分に分けていますが、10分なり30分なりで行ったことを、こんな風にカレンダーにメモしています。
<ピアノ練習 一行日記>
1/24 転(3連複と右手早いパッセージ中心に練習 p5-7 )
1/25 起(P1)、転(P5~の4連符の部分を重点的に練習)
1/26 起(P1を目を瞑って弾く)、承(後半二連打)、転(三連符)
1/27 結(両手部分の合わせる練習を中心に)
1/29 結(P9右手の指使いの確認)、起(P2右手の指使い、左手和音)
これを行い始めてから、上達スピードが上がりました。その理由は、「メモを見返すことで、それぞれのパートでの気づきを思い出せるから」です。
まさに「経験学習におけるリフレクション」だな、と思います。
■まとめ
学生時代に趣味で弾いているときは、ただ闇雲にやるだけでした。
ただ、大人になり、こうした学習理論も理解した上で、それを活用することを考えると、上達のスピードが早くなります。
理論は使ってこそ、活きるものである。
そんなことを感じた次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>