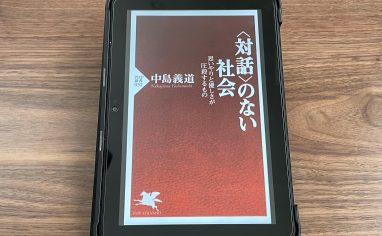おすすめの一冊『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思』
(本日のお話 3454字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、2件のアポイント。
また、社内での「OKRミーティング」の実施などでした。
夜は、大学院の先生と、仲間を含めた会食でした。
(ありがとうございました!)
*
さて、本日のお話です。
本日は、注目の「組織づくりに関する本」からの学びをご紹介させていただければと思います。
ご紹介の本はベストセラー『問いのデザイン』の著者であり、組織づくりの「MIMIGURIデザイン」を創業され、多くの企業の組織変革に尽力されてきた、安斎さんの著書『冒険する組織のつくりかた』です。
============================
『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』
安斎勇樹 (著)
============================
「「新時代の組織づくり論」の超・決定版!」と帯にあるように、時代が変わり、組織も変わることを求められる中で「何を・どのように変えていけば良いのか?」の羅針盤を示してくれる一冊だと感じました。
今日から複数回に亘って、著書の学びをまとめてみたいと思います。
それでは、早速まいりましょう!
■軍事的な世界観から「冒険的な世界観」へ
本書のキーワードは「冒険的な世界観」に組織をアップデートしていく、というものです。
戦略、戦術、PDCA、OODA、アジャイル・・・組織で使われるこれらの言葉は元々「軍事用語」であったことが知られています。
そして同じように、今日組織で働く人々は、”まるで軍隊に所属し、戦争をするかのように仕事をしてきた”、つまり「軍事的な世界観」の中にいたのではないか、と問題を投げかけます。
しかし、今日の社会は変わってきました。
「100年時代」と言われて久しいですが、「会社は人生の一部でしかない」という考えは、より多くの方に広がってきました。
”会社のために自分を押し殺す”という「会社中心のキャリア観」は受け入れられず、”幸せな人生を送るためにどんなキャリアを歩むのか?”という「人生中心のキャリア観」とでも呼べるようなものになっています。
その中で、「会社のために自分を捧げる」「戦略上の役割のために仮面をかぶる」ような軍事的世界観から派生した考えに、特に若い人は違和感を覚えるようになってきているようです。
・・・そんな「軍事的世界観」からは人は逃げ出していき、組織というシステムがますます弱体化していきます。そして、そのために重要なのが「世界観のパラダイムシフトであり『冒険的な世界観』へのアップデートである」と述べています。
■本書の構成
本書は、「冒険的世界観」へのアップデートをするために、前半で「考え方」、後半で「具体的な行動」に分けて論じてきます。
前半では「どんな考え方をすればよいのか?」と、組織に関連する”ものの見方”をどう変えるのかに触れます。そして後半では、ものの見方を行動変容につなげるために「具体的に何をすればよいのか?」を20のキーワードとして紹介します。
―――――――――――――――――――――――――――――――
◎本書の主な構成
[序論]〝冒険する組織〟とは何か?──「軍事的な世界観」からの脱却
[第1部 理論編]冒険する組織の考え方
・第1章 会社の「世界観」を変える──5つの冒険的レンズ
・第2章 自己実現をあきらめない「冒険の羅針盤」──新時代の組織モデル「CCM」
・第3章 冒険する組織をつくる「5つの基本原則」
[第2部 実践編]新時代の組織をつくる「20のカギ」
・第4章 冒険する「目標設定」のカギ
・第5章 冒険する「チームづくり」のカギ
・第6章 冒険する「対話の場づくり」のカギ
・第7章 冒険する「学習文化づくり」のカギ
・第8章 冒険する「組織変革」のカギ
※Amazonの本の紹介より引用
―――――――――――――――――――――――――――――――
■「冒険する組織の考え方」のためのレンズ
では、具体的に冒険する世界観へのアップデートのために、「第一部」の前半では、それらの考え方や理論が紹介されます。
今日は、「第1章 会社の「世界観」を変える──5つの冒険的レンズ」を中心に、紹介いたします。
まず、「冒険する組織」になるためには、以下のようなレンズを持つことが重要、と述べています。
―――――――――――――――――――――――――――――――
<世界観を変える5つのレンズ>
レンズ| 軍事的世界観→ 冒険的世界観
1.目標のレンズ|行動を縛り上げる司令 → 好奇心を掻き立てる問い
2.チームのレンズ|機能別に編成した小隊 → 個性を活かし合う仲間
3.会議のレンズ|伝令と意思決定の場 → 対話と価値創造の場
4.成長のレンズ|望ましいスキル・行動の習得 → 新たなアイデンティティの探求
5.組織のレンズ|事業戦略のための手段 →人と事業の可能性を広げる土壌
P57
―――――――――――――――――――――――――――――――
本書の冒頭では、大人気の漫画『One Piece』を例に「冒険的組織」のイメージを伝えられています。
OnePieceの舞台では登場人物の一人ひとりが、自己実現の目標を持ち、その中で個性を活かしながら冒険をしていく、合理性やMUST感はなく、「ワクワクした旅」のような空気があります。まさにこれが「冒険的組織」のイメージ。
では、そのような世界観のために「どんなものの見方(レンズ)」を手に入れればよいのでしょうか?
上記に紹介された5つのレンズについて、もう少し詳しく解説してみます。
まず、「1.目標のレンズ」では、”好奇心を掻き立てる問い”によって、合理的思考(計画)から野性的思考(創発)を取り戻すことが必要と述べます。
また、今のように市場が予測できない中では「選択と集中」もリスクが高く、「分散と修繕」とやりながら少しずつ軌道修正をしていく考え方が、より効果的になっていると考えられます。
次に「2.チームのレンズ」では、”個性を活かし合う仲間”であることです。
人を道具とみなさない。精神的な共同体とみなし、お互いの個性を見る。その結果、任務別に編成された小隊ではなく、個性を活かし合う仲間になることで、目に見えない「適応的課題」への対処力も高まります。
そして「3.会議のレンズ」では、”対話と価値創造の場”とみなします。
これまで(軍事的世界観)では、会議は上の決定を伝令する場でした。また何かを意思決定する場でした。
しかし、そうではなく、お互いの「対話」(=意見の背後にある前提に目を向ける、考え方や関係性を再構築する)ことが重要であると述べます。対話には「討論・議論・雑談・対話」の使い分けを理解すること、また対話のためのステップ「察知・理解・共創」を理解することが必要と述べます。
また「4.成長のレンズ」では、”新たなアイデンティティの探求”を提案します。これまでは、成長とは「望ましいスキル・行動の習得」でした(例:新人が一人で営業できるようになった、英語が喋れるようになった、など)。この背景にあるのは、”行動主義”といって、観察可能なものを考察の対象とする、長年にわたる価値観が影響しています。
ここから「より”しっくりくる自分像”」を発見していくプロセスを成長とみなす。そうすることで「やりたいことに囚われすぎる」こと、「とにかく承認されたい病」から脱却することに繋がります。
最後に「5.組織のレンズ」では、”人と事業の可能性を広げる土壌”を組織と考えるべしとします。チャンドラーの「組織は戦略に従う」という有名な考えがあります。これは「組織は事業戦略のための手段」と考えました。
一方、それに対するものが、アンゾフの「戦略は組織に従う」です。これは、「変化に強い組織を作り出すから、変化した市場に対応する戦略が作れる」というような考え方です。どちらかと言うと、冒険的世界観では後者です。樹木が成長し続けるごとく、組織の土壌を耕し続ける。組織を生き物と考える事が重要、と述べます。
■まとめと感想
第一章を解説していたら、それだけで長くなってしまいました。一つ一つが共感・納得・発見で非常に惹き込まれます。
特に個人的には、本書における「自己実現の定義」と、「成長の考え方」が刺さりました。
「自己実現=自分の好奇心(=内的動機)に基づいた活動が、他者・社会への貢献や報酬(=外的価値)につながっている状態」と定義する
「外的価値(=周りに期待されるものや喜ばれるもの)と内的動機(=好奇心)が整合することを、諦めずに思考し続ける」ことが、自己実現につながる
そして、それらのプロセスが”新しい自分らしさ(新たなアイデンティティ)”を発見することにつながる
2018年「ティール組織」という本でも、ティール型が組織と個人の目標が一致している事が大事、という話が紹介され、話題になりました。しかし、その際には「とはいっても、現実的に無理なんじゃない?」みたいな空気も私の周りではありました。
しかし、いよいよこうした組織になっていくことが求められる時代になってきた・・・そんな感覚も覚える今日この頃です。また明日も続けてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>