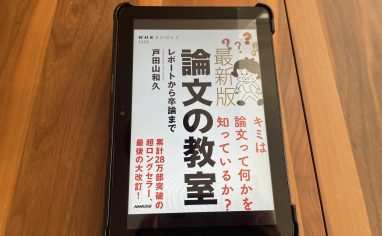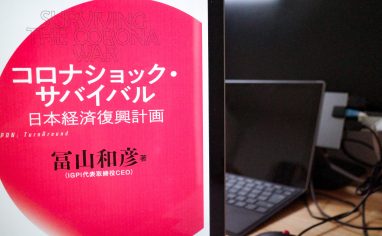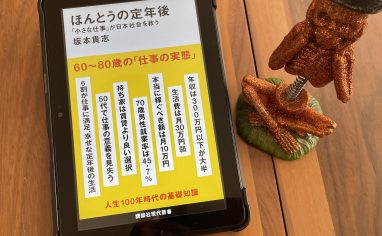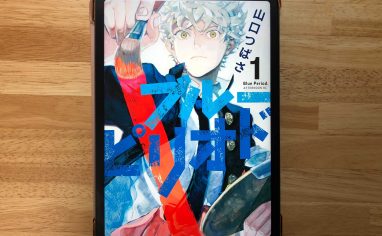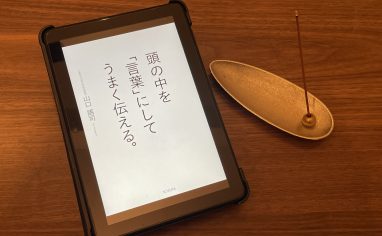おすすめの一冊『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(後編)
(本日のお話 2826 字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、女性リーダー向けの「ストレングス・ファインダー研修」の実施でした。
合計100名を超える女性リーダーの皆さまに全4回行わせていただいた企画も
昨日で終了いたしました。責任感が強く、実直にやるべきミッションを果たす、
大変頼もしい皆さまで、私も刺激をいただいた次第です。
改めて、ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!
また、その他2件のアポイント。
夜は8kmのランニングでした。
*
さて、本日のお話です。
先日に引き続き『冒険する組織のつくりかた』からの学びをご紹介させていただければと思います。本日は後編として、具体的な組織づくりのヒントが詰まっている「第2部:実践編」からの学びです。
それでは、まいりましょう!
(前回までのお話はこちら↓)
https://note.com/courage_sapuri/n/n7526bb0e26d8
――――――――――――――――――――――――
<目次>
新時代の組織をつくるための「20のカギ」
「目標設定」のカギ
「チームづくり」のカギ
「対話の場づくり」のカギ
「学習文化づくり」のカギ
「組織変革」のカギ
感想:本を片手に「やってみる!」が大事
――――――――――――――――――――――――
■新時代の組織をつくるための「20のカギ」
第二部では実践編として、具体的な方法論に触れています。
「目標」「チーム」「会議」「成長」「組織」などの軸において、どんな工夫ができるのか、4つずつアクションリストが紹介されています。
著者の安斎さんが経営するMIMIGURIデザインをはじめ、他社事例を豊富に含めており、「やってみたい」と思えるところからスタートできるようなリストになっています。
ということで、以下「組織づくりの20のカギ」をみてまいりましょう。
◎「目標設定」のカギ
第4章では「目標」について述べられています。冒険する組織をつくるためには、「なぜこれをやるのか?」という”意味”を一人ひとりが理解する必要があります。
もちろん、事業を営む上で、数値目標(KGIやKPI)は必要です。大事なのは、その目標に意味付けをすることによって、”アレンジする”ことが重要であると述べます。たとえば、組織単位で「MVV」を更新したり、目標が設定されたチームで対話をすること、また目標も頑なにこだわるのではなく柔軟に修正をすることなどです。
チェックリストとして「目標設定のリフレーミングのチェックリスト20」などは役に立つと感じました。
KEY1:現場の目標にこそ「追いかけたくなる意味」を込める
KEY2:経営理念は「探求のツール」として活用する
KEY3:目標への納得感を「設定プロセスの前後」で爆上げする
KEY4:目標に違和感が生じたら「迷わず軌道修正」する
*
◎「チームづくり」のカギ
第5章は、チーム作りのポイントです。「自己紹介」についても、自己紹介のフォーマットを作って、お互いの価値観など深いレベルまで理解し合うことや、”チームらしさ”を皆で語り合うこと、そしてそこに時間や金銭的コストをしっかりと投資することの重要性を述べています。
ポイントとして、「お互いの弱さ」や「これまでの個人の歴史」などを語ることで、深い自己紹介をしやすくするポイントなど紹介されています。
KEY5:「深い自己紹介」で心理的安全性を正しく高める
KEY6:「私たちらしさ」とは?チームアイデンティティを言語化する
KEY7:チームの問題解決は「目線合わせが9割」。解くべき問いを見つける
KEY8:「共通体験」のリフレクションで、チームの学びを深める
*
◎「対話の場づくり」のカギ
第6章は「場づくり」がテーマです。「対話」の重要性は、様々な組織づくりの書籍で語られていますが、では具体的に何をすればよいのか? 本書では「ハレ(非日常)」と「ケ(日常)」において、どのような場づくりがよいのかを示しています。
日常であれば、「ファシリテーションはミドルマネジャーは必須のスキル」とし、まただからこそ、”全員ファシリテーションを行うルールを作る”などのMIMIGURIの事例が紹介されます。テクニックとしての、ファシリテーションの個性の違いを活かす方法、対話におけるズレを確認・修正する方法や、定例ミーティングの質の高め方などが紹介されています。
KEY9:「ファシリテーターとしての芸風」を全メンバーで磨く
KEY10:「日々の定例ミーティング」の質を底上げする
KEY11:ハレの場としての「全社総会」に命をかける
*
◎「学習文化づくり」のカギ
第7章では、学び続ける組織づくりのためのポイントが紹介されます。
「学ぶ」とは動画や教材で学ぶのではなく、参加しながら、アウトプットしながら、変化をしながら学ぶなど、その”学習観”の変容を求めています。
またフィードバックも”耳が痛いこと”が必要とか、”ポジティブフィードバックが大事”などを超えて、「目を開かせるフィードバック」として関わることが大事であると述べます。この部分は、現在言われている「フィードバックの新常識」として、ポジ・ネガを超えて、”可能性を開くお手伝いとしてのフィードバック”を提案しているように感じ、特に興味深く感じました。
KEY12:学ぶとはどういうことか?「学びのものさし」を変える
KEY13:育成の要である「フィードバック」の質を変える
KEY14:暗黙知と形式知の「循環」をフィードバックする
*
◎「組織変革」のカギ
第9章は、組織変革をテーマにしています。”変革”という多くの組織がチャレンジしようとしては、なかなかうまくいかないこのテーマに、どのように向き合えばよいのか、具体的な事例が紹介されています。
「変革とは、そもそも”中長期”になるものである」、「やっぱり対話が重要」「危機ドリブンの組織変革は持続性がない(だからチャンス/ビジョンが大事)」「組織の悪いクセを見つける」「企業トップが”覚悟”しなければ変わらない」「文化と構造のどちらにも働きかける必要がある」・・・などなどの、実践知に基づいた示唆が語られており、大変勉強になります。
KEY15:変革は課題設定が9割。自社の「もったいない」を探す
KEY16:トップダウンの変革は「構造」と「文化」をセットで変える
KEY17:ボトムアップの「勉強会」から、変革のうねりを全社に広げる
KEY18:ミドルは変革の中枢。マネジャーこそ「自分」を尊重する
KEY19:「企業アイデンティティ危機」を変革のチャンスにする
KEY20:垣根を超えた仲間へ。健全な「出会いと別れ」をデザインする
■感想:本を片手に「やってみる!」が大事
本書を通読した感想ですが、「理論知と実践知を融合した知恵を、おすそわけいただいている」という気持ちになりました。
MIMIGURIデザインの社内で行われている活動や、他社の組織変革に携わられた経験の中で、「組織づくりで、これは抑えておきたい」というポイントを、考え方と実践例の両方を、説得力を持って、網羅的に伝えていただき、大変贅沢な一冊だと感じました。
そして、タイトルの「冒険する組織のつくりかた」の通り、実際にやってみたい、というワクワク感を喚起させてくれる本でもありました。
あと読者に必要なのは「実際にやってみる」ということだと思います。
もちろん、予想通りにいかなかったり、見立てが違っていたり、ということもあると思います。しかし、経営やマネジャーがこちらの本を共通認識として持ちながら、「やってみよう」としたならば、きっと組織はより躍動的に変わっていくのではないか・・・そのように感じた次第です。
私も人と組織づくりの外部支援者として関わっていますが、体系的に整理をすることにも繋がりましたし、これらの具体的施策をインストールするお手伝いもしてみたいなあ、そんなことも感じさせられた次第です。
人事、マネジャーの皆さまにおすすめしたい一冊でございました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>