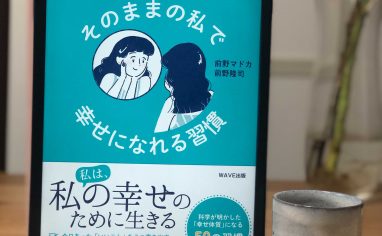おすすめの一冊『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか』
(本日のお話 3453字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、MBTIの認定ユーザーの資格取得の試験でした。
ゆるっとした試験かと思いきや、かなりガチ目で、合格率は半分を切るとかなんとかいう噂も聞きました。
試験が13:30から始まり、私は早めに終わったほうがですが18:00までかかりました。
時間制限はないので、中には20:30までかかった人もいたそうです。
文字を久しぶりに大量に書いたので、腱鞘炎になりそうでした(汗)
合否は微妙そうですが、とりあえず終わったので良しとします。
*
さて、本日のお橋です。
毎週日曜日は、最近読んだ本の中からご紹介する「おすすめの一冊」のコーナーです。
今回の本はこちらです。
本書は、「新書大賞2024」第1位を獲得、アジア・ブックアワード2024「最優秀図書賞」(一般書部門)受賞した、2024年のベストセラーの一冊です。25万部を突破した、話題の本でもあります。
==========================
『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか 』
今井 むつみ (著), 秋田 喜美 (著)
==========================
読んでみた感想ですが、「めっちゃ面白い」です。しかも、深い。
科学的に「言語の獲得」について検証した結果や、過去から続く認知科学の難題、「AIに愛情はわかるのか?」という気になる問いについて専門的な観点を噛み砕いて読者に伝えてくれます。
といことで、早速中身を見てみましょう!
■「言語が持つ力」とは
「言語は人間のみがもつ能力である」。そんな話を聞いたことがあります」。実際に言語が人間と他の動物を分かつ特徴であることは、多くの言語学・認知科学の研究者によって支持されている主要な考えです。
たしかに、そのとおりで言葉なくして、ぼんやりとイメージのまま深い思考をすることは難しいです。言語を獲得し、複数の言葉を組み合わせることで、様々な事象や行為に個別の意味を与え、分化させることが可能になりました。そうして、人は深く考えることが可能になり、知性が発達する源となりました。
また自分の思考を深めるだけでなく、言葉によって複雑な思考・感情を共有することで、集団としての発展も可能になりました。言語を習得することで、時間・空間を超越して、知見が共有されることも可能になりました。
まとめると、「言語が持つ能力」には、以下の4つがあるとのこと。
<言語が持つ能力>
1,超越性:時間と空間を越えて抽象的な話題を扱える能力
2,二重性:限られた数の音を組み合わせて無限の表現を生み出せる能力
3,規則性:複雑な文法体系を持つこと
4,学習能力:言語を自律的に学習し、運用する能力
ただ、何となく使っている「言語」、日本であれば日本語について、その特徴を考えることもなければ、どのように言語を習得していくのかを考えることもありません。
■本書の内容
そんな「言語」について、言語学・認知科学の専門家が、言葉の歴史、言語学の研究などを縦横無尽に歩き回り、私達の無意識の軸となっている「言語の世界」の水先案内人になっていただけるのが本書です。
主に、人間の言語の萌芽となったとされる「オノマトペ」について注目しながら、「赤ちゃんがどのように複雑な言語を学習していくのか?」、また「言語がそれぞれの文化でどのように発展していったのか?」、などについて考察されていきます。
以下、具体的な内容と目次について、引用いたします。
(ここから)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■本書の内容■
日常生活の必需品であり、知性や芸術の源である言語。
なぜヒトはことばを持つのか? 子どもはいかにしてことばを覚えるのか? 巨大システムの言語の起源とは? ヒトとAIや動物の違いは?
言語の本質を問うことは、人間とは何かを考えることである。
鍵は、オノマトペと、アブダクション(仮説形成)推論という人間特有の学ぶ力だ。認知科学者と言語学者が力を合わせ、言語の誕生と進化の謎を紐解き、ヒトの根源に迫る。
■本書の目次(一部抜粋)■
はじめに
言語という謎/記号接地という視点/言語の抽象性――アカを例に/言語の進化と子どもの言語習得の謎
第1章 オノマトペとは何か
「オノマトペ」の語源/オノマトペの定義/感覚イメージを表すことば?/写し取っている記号?/他
第2章 アイコン性――形式と意味の類似性
単語の形のアイコン性/音のアイコン性――清濁の音象徴/続・音のアイコン性その他の音象徴/発音のアイコン性――角ばっている阻害音、丸っこい共鳴音/他
第3章 オノマトペは言語か
言語の十大原則とオノマトペ/音声性・聴覚性/コミュニケーション機能/意味性/超越性/継承性/習得可能性/生産性/経済性――言語になぜ経済性が必要か/他
第4章 子どもの言語習得1――オノマトペ篇
子どもが小さいほどオノマトペを多用する/絵本の中のオノマトペ/オノマトペは言語の学習に役に立つのか/音と形の一致・不一致がわかるか/ことばの音が身体に接地する第一歩/名づけの洞察――ヘレン・ケラーの閃き/クワインの「ガヴァガーイ問題」/他
第5章 言語の進化
言語の理解に身体性は必要か/永遠のメリーゴーランド/AIは記号接地問題を解決できるのか/一般語と身体性/音と意味のつながり/隠れたオノマトペ/オノマトペと日本語の方言/なぜ言語・地域固有性があるのか 他
第6章 子どもの言語習得2――アブダクション推論篇
ガヴァガーイ問題再び/一般化の誤り――かわいい事例から/「ポイする」/オノマトペを疑う/最強のデータベース、身体を持つロボット/ニューラルネット型AI――ChatGPT/記号接地できずに学べない子どもたち/ブートストラッピング・サイクル/他
第7章 ヒトと動物を分かつもの――推論と思考バイアス
チンパンジー「アイ」の実験/非論理的な推論/動物はしない対称性推論/対称性推論のミッシングリンク/他
終 章 言語の本質
本書での探究を振りかえる/AIとヒトの違い 他
Amazon本のレビューより
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(ここまで)
■読んで印象に残ったこと
本書では、「オノマトペ」が言語の萌芽であり、かなりの紙面を割いて、語られていました。別の本で「音象学」について書かれた本では、「『あ』は 『い』より大きい」という印象を持つとか、丸っこい言葉(マルマ)や角張った言葉(タケテ)は文化を超えて共通する、とか長くなるほど強いイメージになる(「ホイミ→ベホマズン」とか「ピチュ→ピカチュー」など)を説明しています。
このような「音が持つ印象」に加えて、見た目や音の雰囲気を含めた「コロンコロン」「ゴロンゴロン」というオノマトペこそが、赤ちゃんが、この世界に降り立ち、言語に触れ、言葉のルールを覚え、そして学習していくルールが含まれている、と述べています。
▽▽▽
また、「記号接地問題」という認知科学の未解決の問題の話も興味深いものでした。たとえば「AIは『恋』を理解できるか?」という話について考えてみます。ChatGPTに「恋とはなにか?」の説明を求めると、「恋」という意味を持った記号(言語)を、別の言語で説明するでしょう。
たとえば「切なくて、胸がぎゅっとする感情」を伴うものと説明するかもしれません。でも、”胸がぎゅっとする感情”はわからないし、この”ぎゅとする感情”を別の記号(言語)で表現したとしても、それは記号で記号を説明するに過ぎません。(この状態を『記号から記号のメリーゴーランド』というそう)。
つまり、どこかで身体的な経験を持たなければ(接地していなければ)、その言葉を本当にわかったとはいえない、という話です。これは「AIは、”本当に”恋”が理解できるのか?」という哲学的な問いにも繋がり、今なお議論がされているようです。
▽▽▽
また「ガヴァガーイ問題」という話も紹介されていました。
たとえば、ある未知の言語を話す原住民が、”野原を跳びはねていくウサギのほうを指さして、「ガヴァガーイ!」と叫んだとします。
そのときに「ガヴァガーイ」の意味は何か?と考えると「ウサギ」と考えられますが、実際は、”飛び跳ねる動物”を言ったのかもしれないし、”白い毛”を言ったのかもしれないし、”白いフワフワした動物”といったかもしれないし、”うさぎの肉”といったかもしれない、、、つまり、一つの指示対象から一般化できる可能性はほぼ無限にある、という話です。
そしてこれは、ことばを学習する過程で、こどもたちが直面する問題でもある、と述べます。そして実際にこれら問題を検証するために、子どもたちに実験を行う話もあり、興味深いものでした。
■まとめと感想
この本を読んでから、息子(4歳)が、どんなふうに言語を習得しているのかが気になるようになりました。
そして、推論をしやすく「私は・・を~~した」というSVO文型を大事に話したり、また言葉の推論が難しそうなときは、その行為をサポートするような補足を入れることで、彼の言語習得が進んでいる(ような気がする)のでした。
言語を知ることは、人間を知ること。
そんな事を考えさせられるおすすめの一冊でございます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>