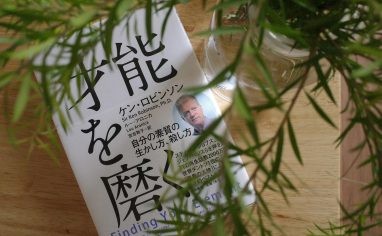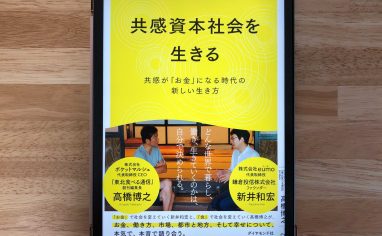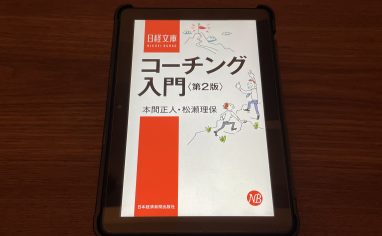親戚との食事会で感じた「微妙なズレ」から「対話の難しさ」を考えた話。。
(本日のお話 3353字/読了時間4分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、静岡に出張。
空調設備の会社の皆様への「リーダーシップ研修」の実施でした。
皆さま、なれないワークにも前向きに取り組んでいただき、かつご自身の発見も口に出していただき、
大変ありがたく思う時間でした。改めてご参加いただき、ありがとうございました!
また、夜は親戚との食事会でした。
*
さて先日、母より突然、「東京に親戚に会いに行くから、一緒に夕食でもどう?家族も一緒に」と連絡がありました。
親戚とは、私の96歳になる祖母の妹とのことで、今年80歳になる女性です。そして、母、叔母、私と妻と息子(4歳)、そしてその方という、なんとも不思議な組み合わせで、食事をすることになりました。
その時の内容が、「対話」という観点で、なかなか学び深きものであったので、振り返りも含めて、言葉にしてみたいと思います。個人的な話ではありますが、よろしければお付き合いくださいませ。
それでは、どうぞ!
―――――――――――――――――――――――
<目次>
80歳、商売人、パワフルなおばあさん
食事会で感じた「微妙なズレ」
食事会で、何が起こっていたのか?
「対話の場づくり」は技法が必要である
――――――――――――――――――――――――
■80歳、商売人、パワフルなおばあさん
個人的な話ですが、私の曽祖父・祖母の時代に、中国から日本にやってきました。親戚には、中国の名字の人もちらほら。そして「商売人」が多いです。かつ、言葉が強く、クセもすごく、金に執着がある人も多い印象です。(個人的には、こういう特性はあんまり好きではないのですが(汗))
今回会った私の遠い親戚のおばあさんも、今年80歳になるのですが、まさに「商売人」という感じでした。出てくる言葉の数々が、それを物語っています。
現在も、齢80歳にて、ChatGPTを駆使して事業を進めているそう。旦那さんの病院の経営をしつつ、虎ノ門ヒルズにご自宅があり、お子さんはお医者さんやマッキンゼーなど勤められているそう。
親戚にもいろんな人がいるんだなあ、、、と感じていました(遠い目)。
■食事会で感じた「微妙なズレ」
さて、そんな親戚のおばあさんとテーブルを囲む私と叔母、そして母。
叔母は区役所に勤めており、生活が難しい人たちの相談に乗っています。そして母は一般サラリーマンの家。市場でバイトをしたり、現在は祖母の介護をしながら卓球をする日々。そして私と妻、またプラレールしか見えていない息子。
同じ血筋とはいえ、生きている文脈が違います。その中で、食事会なので雑多な話が繰り広げられます。
▽▽▽
たとえば、「AI」について話題が出ました。叔母さんの意見に対して、親戚のおばあさんは「それは違うと思う」と、ズバッといいます。すると、場に一瞬の緊張が走る。その後は、議論を好みそうなおばあさんとこだわりの強い叔母さんの一騎打ち感が出ます。一方、そうしたピリピリ感が好きではない妻と母は、バツの悪そうな感じで席を移動します。
そして続いて、私も参戦して「AIでは、”人間の葛藤などの感情”を踏まえた意思決定は難しい気がします」と話を投げかけてみると、親戚のおばあさん。「組織はピラミッドであり、より立場の上の人が多くの給与をもらっているんだから、その人が尊敬を集めて引っ張っていくべきである」という主張が重ねられました。
うーん、確かにそうなんだけど、私が伝えたいニュアンスとズレたような・・・。言葉の真意を受け取られないまま、違う意見を重ねられると「微妙なズレ」が生じる感覚が起こります。かつ、強い語気にさらされると、自分の意見をなんとか伝えようというモチベーションが削がれる感覚も持ったのでした。
全体としては「親戚のおばあさん」が持論を語り、それを周りが聞くという構造が生まれ、そして食事会の幕を閉じたのでした。
話自体は面白く、おばあさんすげえな、、、、という感じだったのですが、これを「対話」という観点からみた時に、考えさせられるものでもあったのでした。
■食事会で、何が起こっていたのか?
さて、食事会の帰り道「この食事会で、何が起こっていたのか?」を、場を共にしていた妻と振り返りつつ話をしていたのでした。
そのときの「食事会のまとめ」を3つに絞ると、以下のようなものでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<食事会からの教訓>
1.人は使っている言葉から、その人の”大事にしているもの”が垣間見える。初めて会った人でも、どんな内的世界に生きているかは感じられる。
2.「対話」のためには、相手が見ている世界を知る事が必要。そのためには、相手の話を聞ききる事が重要であり、忍耐も必要である。
3.共通の目的がなければ、対話は難しい。なぜならば「主張をする人」に対して、自分の主張を返そうというモチベーションが生まれないため。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず「1.人は使っている言葉から、その人の”大事にしているもの”が垣間見える」についてですが、親戚のおばあさんの話には、率直に言えば「権威」「稼ぐこと」「自立すること」などへのこだわりがにじみ出ているように感じた、という話がありました。
たとえば、話の中で「◯◯大学の教授が言っていた話」「950万円のバッグを買おうか迷った話」「息子さんのやっている300億の国家主導のプロジェクト」などの言葉が並びました。言葉はその人の思考の表出なので、その人の内的世界は、きっとそれが重要であるということ。
一方、それを聞いていた妻は「正直、教授がどうとかどちらでもよい」と思っていたそうで、このあたりに価値観のズレが生まれるようで、興味深いです。また憶測ながら、中国家系の刻み込まれた「商売人魂」みたいなものもあるように感じられました。(繰り返しますが、80歳です)
そして、「2、「対話」のためには、相手が見ている世界を知る事が必要」ですが、相手の言葉は、相手の見ている世界の一部を切り取ったにすぎません。そこの真意を理解しない状況で、ガツっと違う意見を強く重ねると、「微妙なズレ」が生じます。でも、実際にほとんどの会話はこういうものなんだよなあ、、、と思わされる時間でもありました。
最後に「3.共通の目的がなければ、対話は難しい」についてです。今回は食事会でしたので、好きなように「議論」で自分の主張をぶつけても、「雑談」ととりとめなく話しても、全くの自由です。今回は「親戚のおばあさんの講演会」のような形になったわけですが、これはこれで興味深く、面白かったのでありです。
しかし、私(紀藤)は、親戚のおばあさんの強い語気を見て、私はそこに自分の意見を混じり合わせるのは難しそうだな、と思い、聞き役に徹することになりました。もし、親戚のおばあさんと、仕事などで「共通の目的」があれば、粘り強く自分の意見をわかってもらおう思ったかもしれません。
ただそこにルールがない場合、「主張をしたい人」と「それを聞く人」のような構造に自然と分かれて、それぞれが実は色々と思っている、ということにもなる可能性があります。
とすると、集まった場を「皆にとって満足が行く場」にするためには、それぞれがどういう世界を見ているのか、ほんのりと想いを馳せること、つまり「対話モード」であることのほうが、よりメリットも大きいように思いました。
■「対話の場づくり」は技法が必要である
そして、妻との振り返りの結論は、「対話は簡単ではない」ということでした。
違う世界に生きている人が、同じ景色を見て、それぞれ深く理解し合うこと。なんならそこから共通の方向性を合意し、決断をすることはいろんな技術が必要である、、、そんなことをしみじみ感じたのでした。
話し合いの要素には、以下の4つがあると述べられています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
<話し合いの4つの要素>
1,話し合いとは、人々が身近な他者とともに働いたり、学んだり、暮らしていくために、
2,自分が抱く意見を、お互いに伝え合い(=対話)
3,他者との「意見の分かれ道」を探り合い、メリット・デメリットを考え
4,自分たちで納得感のある決断を行い、ともに前に進むこと(=決断)
※引用:中原淳(2022)『「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法』.PHP研究所, P6-7
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
こうした実りある対話の場を作るには、「主張したいだけの人」がいても定まらないし、「どっちでもいいやという人ばかり」でも進みません。
最近の私の周りの人が、基本「どんなときも対話モード」、つまり”相手の話を受け取って、そこに自分の意見をポトンと落とす”ような話し方をするのが多く、それが当たり前になっていましたが、必ずしもそうではない、というのが刺激的かつ、気付かされる機会になったのでした。
「成り行きに任せて、皆が深く理解し合える場になることは難しい」ということは、今回の食事会を振り返りつつ、思うことでもありました。
人々が対話をすることの難しさを、ふと感じた夜でございました。
(繰り返しますが、食事会自体は、実に楽しい時間でした!)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>