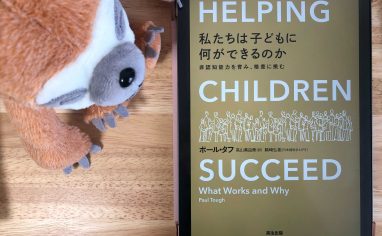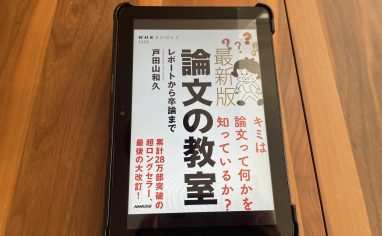「毎週一冊のまとめ記事」を書き続ける3つのポイント
(本日のお話 2354字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日金曜日は、引き続きストレングス・ファインダー研修の実施でした。
参加者の皆様の「自分の強みの理解が深まった」という感想も大変嬉しいものでした。
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました!
*
さて、本日のお話です。
先日、大学院の仲間から「普段、どんな風に読書してますか?」と質問をいただくことがありました。
内容はともかく、一応4000号以上続けているメルマガにて、毎週日曜日に「おすすめの一冊」として、今週読んだ本の感想を記事にしていることを見て、読書の読み方に興味をもっていただいたとのこと。ありがたいことです。
大した内容を書けているとは全く思いませんし、読書も得意とは全く思っていませんが、自分なりの「読書」における読み方のポイントを、言葉にしてみたいと思います。
参考になるか不明ですが、よろしければお付き合いいただけますと幸いです。
それでは、どうぞ!
―――――――――――――――――――ー
<目次>
(1)買うポイント→「ビビっときたら即ポチる」
ビジネス書はKindle、専門書は紙の本
(2)読むポイント→「その時読みたいもの」を読む
同時に何冊も読み進める
ビジネス書はささっと、専門書はじっくり読む
(3)まとめるポイント→ 「人に説明するとしたら?」
まとめと余談
―――――――――――――――――――――
■(1)買うポイント→「ビビっときたら即ポチる」
本の選び方・買い方ですが、私は2つのポリシーがあります。
「その1.ビビッときた本は、即購入(即ポチる)」
「その2.信頼おける人によるおすすめの本は即購入(即ポチる)」
です。
ちょっと気になる本の場合は、「Kindleの無料サンプル」で読んでみて、それでも気になるようだったら買います。
こうすると、それなりの冊数買うことになり、お金がかかります。
しかし、読書はセミナーなどに比べて格段に安いですし、「最大の投資は自己投資」と、私の友人のファイナンシャルプランナーが言っていたことを信じ、書籍代についてはお金に糸目をつけず、何よりも優先してお金を使うことに決めています。
ちなみに「ビビッときた」だけで買っていると、ビビッと来すぎて、どんどん積読が溜まっていきます。
でも、それでもいいやとしています。
というのも、時間を経て「読んでみたい熱」が高まって読むこともあり、時差的に読むタイミングが来ることもままあるからです。自分の未来へのプレゼントですね。
◎ビジネス書はKindle、専門書は紙の本
ちなみに、よくある疑問が「紙が良いか,電子が良いか」という意見です。
私の場合、基本的に「ビジネス書や新書はKindle」で、「専門書は紙の本」としています。理由ですが、専門書は色々と自分なりにメモをしたり、書き込むことが多いからです。
なので、思考を熟成し、ノート代わりに書き込みたい本は、書きやすい・メモをしやすい紙の本にしています。もちろん、ビジネス書などでも、骨太のものは紙の本で買います。判断基準は、著者や出版社から類推しているので、直感的なところもあります。
あまりにも良いものは、紙と電子どちらも買っているものもあります。
■(2)読むポイント→「その時読みたいもの」を読む
さて、本の読み方ですが、「本」は読む気分ではないものを読んでいても、全く頭に入ってきません。なんなら速攻で眠たくなります。というか実際寝ます。
なので、「今、自分が読みたい本」を読むことをルールにしています。MUSTではなくWILLを大事にしています。今の状況、興味・関心、気分諸々、気になった時が一番”乾いているとき”であり、浸透率が高いからです。
◎同時に何冊も読み進める
読んでいて1冊の本にちょっと飽きてきたら「別の本を読む」こともあります。なので、同時進行でいくつも読んだりします。これが「(1)本の買い方」にも連動するのですか、いくつもストックがあると、この読み方が可能になりますし、実はそのほうが漆塗りのように読むので記憶にも残りやすいと感じます。
◎ビジネス書はささっと、専門書はじっくり読む
専門書に比べ、ビジネス書のほうがページ数も少なく、また読みやすくささっと読める物が多い印象のものがあります。イメージは、一節に一つのキーワードをゲットできればいいかな、という感じかも知れません。
専門書は、一行に含まれている情報も多く、正確に読み解く必要があるので、時間がかかります。また引用論文などあると、そこも寄り道をすると少し時間がかかる印象もあります。
なので、「おすすめの一冊」も忙しくて、読む時間まとめる時間がないときは、「簡単そうなビジネス本」を選んで、1時間で読んで、さっとまとめるようにしています。最近、こればっかりの気もします(汗)
■(3)まとめるポイント→ 「人に説明するとしたら?」
ちなみに本はびっくりするくらい忘れます。正直、毎週本のまとめを書いていますが、それでもまとめた内容をリガンガン忘れます。
自分はアホなんじゃないか、と思うこともあるほど。でも自分以外の人々も、多分そんなものなのかな、という気もします。
それでも、なんとか忘れないためのポイントが、結構「本をまとめること」になります。本が言いたいことは何なのか?自分なりの言葉でまとめようとするプロセスそのものが学びになります。
まとめる際は「この本良かったよ!こんなことが書いてあって,こんなところが学びになったと、説明するつもりで読む」と、その後まとめやすくなる気がします。つまり、説明するつもりで読んでまとめようね,という至極普通のことが、まとめるポイントかと思っています。
結局まとめても忘れるのですが、読み返すと「あー、そんなことまとめた気がするなあ」と記憶が復活すること、いくら忘れても,一応文字としてまとめが痕跡として積み重なって、学んだ感じにつながるのも、グッドです。
■まとめと余談
ちなみに、私の場合,積読になった本,ある程度読んだ本はブックスキャンというサービスでPDFにしています。Kindleにもできますし、PDFで読むこともできます。また、Kindleの場合は、「iPad mini」が文庫サイズになり、携帯性含めて読みやすくておすすめです。
図書館も一時期使っていたのですが、同時進行で読むことから、結局、返却期限に間に合わないなどで、あまり活用できませんでした。
ということで、ゆるっと書いてみましたが、何かしらのご参考になれば幸いです。最後までお読みくださり,ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>