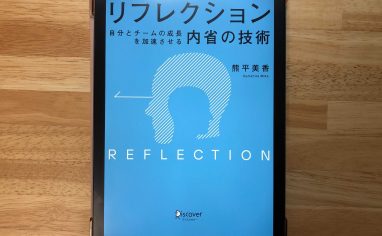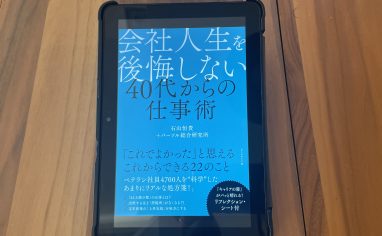感情に上手く対処する「感情調整」の鍛え方 ー読書レビュー『非認知能力』#10
(本日のお話 2711字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、組織分析を行わせていただいた会社への
リーダーシップチームの皆様の組織開発のサーベイフィードバック&チームビルディングでした。
簡単ではない状況の中で、リーダーシップチームの方々が力強く、頼もしく、これからに組織に希望を感じる時間で、なんだかぐっと来るものを感じていました。
皆様のこれからの旅路が、素晴らしいものになりますように。
*
さて、本日のお話です。
先日より「非認知能力」について学べる専門書をご紹介しています。
引き続き、本日も読み解いてまいります。
本日取り上げる非認知能力は、”感情にうまく対処する能力”である『感情調整』です。
この「感情調整」なる能力はOECD(経済協力開発機構)でも、子どもたちが望ましい成果(心身の健康や学業成績)の達成のために必要な社会情緒的スキル・非認知能力であると定義されています
実際に読んでみたところ、子育てにも大切なポイントが書かれていて、なるほどなあ・・・と勉強になったのでした。
ということで、早速中身をみてまいりましょう!
―――――――――――――――――――――
<目次>
「感情調整」とはなにか
感情調整の3つの機能
感情調整のプロセス理論
感情調整と「望ましい結果」の関係
感情調整を伸ばすための介入研究
介入方法1:「感情」に名前をつける練習をする
介入方法2:気持ちを表す言葉の教育
まとめと感想
―――――――――――――――――――――
■「感情調整」とはなにか
私たちは、家庭、職場、学校などの生活中で、嬉しい、楽しい、腹が立つ、悲しいなど、様々な感情を感じています。そうした中で、状況に応じて、感情を表情や言葉で表したり、時には感情を表出させないように我慢したりして社会生活を行っています。
こうした行為に関する概念を「感情調整」と呼びます。
◎感情調整の3つの機能
感情調整は、様々な目的のために行われます。その中で、感情調整の特徴として、以下のような3つの機能が書かれていました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<感情調整の特徴>
1.感情を望ましい状態に保つ
※例:友達の悩みを聞くために、笑顔を消す(ポジティブ感情を低める)
2.自分(または相手)の感情を調整する
※例:自分がイライラしたときに、落ち着こうとする(内的感情調整)
※例:アイスを落として泣いている子どもを、なだめようとする(外的感情調整)
3.感情調整は意図的にも自動的にも行われる
※意図的に行われるものを「顕在的感情調整」自動的に行われるものを、「潜在的感情調整」と呼ぶ。それが変化していくこともある。(たとえば、はじめは仲間外れにされたことに起こった表情を意識して隠していたのが、それが常態化される中で、無意識に表情を消すようになったなど)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*
◎感情調整のプロセス理論
そして、感情調整を捉える枠組みとして「感情調整のプロセス理論」なるものがあります。
これは感情調整が5つのプロセス(選択→状況→注意→評価→反応)を経て生起すると考え、以下のようなプロセスとして表現されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<感情調整のプロセス理論>
1.状況選択:ある感情を喚起させる状況を選んだり、避けたりするプロセスのこと。
(例:学習する科目や場所などの状況を選ぶことなど)
2.状況修正:状況を直接変えるプロセスのこと。
(例:テスト中に問題を解く順番を変えるなど)
3.注意配置:注意を向けたり、逸らしたりするプロセスのこと。
(例:週末に喫茶店で自習するときに、周囲の会話に気を散らされないよう、イヤフォンをして音楽を聞く)
4.認知的変化:状況の評価や捉え方を変えるプロセスのこと。
(例:大学入学テストが直前に迫ったとき、十分に勉強したことを思い出し、合格できるだろうと期待すること)
5.反応調整:表情やしぐさといった反応を変えるプロセスのこと
(例:授業中に退屈している時に、あくびをこらえるなど)
P152-P153
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■感情調整と「望ましい結果」の関係
さて、これまでの研究から感情調整が、様々な結果に関連していることが示されてきました。
まず、306の実験結果を調べたメタ分析によると、ネガティブな感情が喚起されるときに「認知的変化」(ポジティブに捉え直そうとする)ことが一貫して「心の健康」への効果があることが示されました。
さらに、学業成績との関係では、
・感情調整がうまく行える園児は、数え方や読み書きを正確にできる
・感情調整を上手く行える小学生は、算数の成績が良い
・感情調整をうまく行える中学生は、国語と数学の成績がよい
ことが示されました。
学業成績に影響する理由は、幼児期において「言語と感情の理解が発達する」ことで、児童期で「感情を調整する能力が発達」し、先生や友達との関係が良好に保たれ、学業成績に影響すると考えられているそうです。
■感情調整を伸ばすための介入研究
では、感情調整を伸ばすために、どのような介入方法があるのでしょうか。
代表的なものとして「情緒知能」の章でも紹介した「RULER」という学習プログラムが効果があることが示されています。
◎介入方法1:「感情」に名前をつける練習をする
この中で、特に就学前の園児の感情調整を助けるための具体的な方法が書かれていました。以下引用いたします。
”大人が一日を通して、感情に名前をつけ、感情を言葉で表したり、指導し助けたりすることで、子どもが怒りやイライラと言ったネガティブ感情を調整する練習の機会を提供することができる”
たとえば、「靴が履けなくて、イライラしているんだね」とか「アイスクリームを落として、悲しいね」などです。
◎介入方法2:気持ちを表す言葉の教育
ちなみに感情を感じる力も、次第に発達をしていきます。
最初は、「喜び」「悲しみ」「怒り」などだったものが、学年が上がると、それぞれの強度を感じられるようになったり、「モヤモヤ」「憧れ」「嫉妬」などの他の感情も覚えるようになっていきます。
どのような感情を感じているのかを認知することが、感情調整のステップになるため、感情の名前を覚え、表現していく練習が有用であるとのこと。RULERでは、具体的に、以下のような6段階ステップで教育方法が紹介されていました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<気持ちを表す言葉の教育(Feeling Words Curriculum)>
第1段階:楽しかったり嬉しかったことを話し合い、教師はその感情を表す言葉を紹介する(例、喜び)
第2段階:感情を表す言葉を絵で表現し、説明する
第3段階:感情を表す言葉を用いて、授業で取り上げた物語の登場人物の感情を短い文章で述べる(例:友達からの手紙を待つ主人公の気持ち)
第4段階:家で保護者に対して、授業で話した感情を表す言葉を説明し、どんな時に経験をしたか質問する
第5段階:第3・4段階で取り上げた内容についてお互い話し合う
第6段階:感情が変わっていった人の物語を創作する
P160-161
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■まとめと感想
この章を読みながら、映画『インサイド・ヘッド』のことを思い出していました。主人公の少女ライリー(11歳)の頭の中にある感情は、最初は「よろこび、かなしみ、いかり、びびり、むかむか」の5種類でした。
しかし、『インサイド・ヘッド2』になると、少女ライリーは思春期を迎え、高校入学を目前にする15歳になります。ここでは新しい感情として「シンパイ、イイナー、ダリィ、ハズカシ」が加わっていました。この話も、なんだかこの章に通ずるものがあると感じました。
また、私もこの章を参照に、息子(4歳)の感情を表現する助けを引き続きしてきたいな、などと思った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>