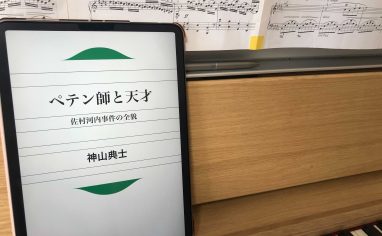「才能」は遺伝子だけで決まらない ―読書レビュー『遺伝マインド』#8
(本日のお話 3824字/読了時間5分)
■こんにちは。紀藤です。
昨日は、立教大学のビジネスリーダーシップコースのBL2(2年生のリーダーシップ)の初回の授業でした。
チームビルディングとのことで、学生に混ざって私服で机に座っていたら、
男子学生が、「教室わかった?」と学生と勘違いしてくれたようで、なんだか嬉しくなった1日でした。
その他、夜は5kmのランニングなど。
*
さて、本日のお話です。
先日より、遺伝子が心や行動に与える影響を科学する「行動遺伝学」をテーマに学びを共有しております。
本日は「終章 遺伝マインドで考える」より、ここまでの第1~5章までを振り返りつつ、全体のまとめと「遺伝マインドで考える社会とは?教育とは?才能とは?」という話へとつなげていきたいと思います。
それでは、どうぞ!
■「遺伝マインド」のここまでのお話
これまで、第1章から第5章までにわたって「遺伝マインド」について語ってきました。(これまでのお話はこちら↓↓)
「第1章 遺伝子と多様性」では、まず人間がいかに多様で進化的な存在であるかを確認しました。私たちは高度な社会性を持つ動物であり、その根底には遺伝子がある。DNAの塩基配列は、生命の“普遍性”と“個別性”という二つの側面を同時に映し出します。
そして、遺伝子とは、約40億年にも及ぶ歴史を持つ、全文化的な存在でもある。その意味で、我々が遺伝子を理解しようとする時、そこには文化的な解釈が必然的に介在してくる――この点には注意が必要であると述べました。
「第2章 ふたごのはなし」では、双子の研究を通して、人間の心や行動の個人差がいかに遺伝の影響を受けているかを見てきました。遺伝、共有環境、非共有環境という三つの要因が、私たちの個性に影響を与える枠組みとして紹介されました。
「第3章 遺伝子のはなし」「第4章 遺伝子のはなしつづき」では遺伝子そのものについて掘り下げ、「私とは何か」を遺伝的視点から考えました。ここでは特に、1)あらゆる行動の個人差に遺伝子が関与していること、2)心や行動のさまざまな側面(認知能力とパーソナリティなど)は遺伝子によってつながっていること、3)遺伝の影響は時間や環境によって変化すること、という三つの柱を押さえました。
「第5章 環境のはなし」では環境の話へと進み、特に「共有環境」の影響が想定以上に小さいこと、つまり家庭や教育環境が子どもたちに与える影響は限定的であるという、衝撃的な事実を共有しました。
そして、「終章 遺伝マインド」へ続きます。
■「遺伝マインド」とは一体なにか?
さて、終章となる今回は、改めて「遺伝マインド」とは何かを考えます。
以下、本書からの一部引用しつつ、私なりにまとめます。
“遺伝マインド”とは、人間一人ひとりの「心の自然」からの由来を誠実に認識しようとする態度のこと。
心や行動も、生命現象であり、環境に適応しようとする働きのひとつ。その中には、遺伝的な営みの姿が見え隠れしている。心や行動は、環境の影響であるという環境マインドで、遺伝子の働きを「見て見ぬふり」するのではなく、正面から見ようとする。それが遺伝マインドの核心である。
私たちは、つい陥りやすい「環境マインド一辺倒」――すべては努力や教育で変えられるという見方をしがちです。しかし、実際の研究では、たしかに心も行動も、遺伝子の影響を受けている。このことを「鏡の背面」として受け止めようじゃないか、といっているわけです。
そして同時に、遺伝マインドは「遺伝子決定論」、つまりこの遺伝子があるからこうなる、というような安易な見方に対する批判的視座も強調しています。
■遺伝子たちはオーケストラを奏でている?!
その上で、本書では「単独遺伝子で行動や特性を説明できるものは、ほぼない」といっています(少なくとも現在の研究では)。
たとえば、「COMT遺伝子と認知能力や統合失調症との関連」また「MAOAと虐待経験が反社会的行動に及ぼす相互作用」など、本書では3つほどのケースを紹介していますが、それでも、特徴的な単独の遺伝子が説明できる個人差は、せいぜい数%に過ぎません。
大事なのは、*「遺伝子たちには協同プレーによって働いている」という点です。以下、引用いたします。
―――――――――――――――――――――
“これはとりも直さず、人間の心や行動に及ぼす遺伝の影響が単独の遺伝子によってもたらされるのではなく、数多くの遺伝子たちの協同プレーとして現れていることを意味する。
これはベルリンフィルとウィーンフィルの出す音色の違いを特定の奏者の音質の違いで説明しようとすることに例えられる。
オーケストラのような多くの要素のダイナミックな集合体として作り出される「音色」は、一人一人の微妙な音の出し方の違いが合わさり、その総和と相乗の全体として現れてくるものであって、どの特定のバイオリン奏者がどういう音を出したからこのような音色の違いが生じたというものではない。
同じように、たくさんの遺伝子のひとつずつのわずかずつの影響が合わさって生まれる全体の効果が、その人の遺伝的特質となる”
P160
―――――――――――――――――――――
そして、ビッグファイブなどで、パーソナリティを5つの要素にわけて、それが文化を超えて信頼性があると説明したのは、たとえば膨大な遺伝情報のパーソナリティの側面をある括りで説明したということになります。
先のオーケストラのたとえに合わせるとは「オーケストラの一部が、”弦楽器(第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス)で成り立つと説明した」ようなもの、と述べています。
なんとも、おしゃれなたとえです。
しかもわかりやすい・・・!
■教育・社会・才能を“遺伝マインド”で読み解く
また“遺伝マインド”の視点から、教育や才能について見てみましょう。
まず、私たちの「社会」です。ここには想像を超えた遺伝子多様性が存在しています。個人の遺伝子の差異は0.1%に過ぎないと言われても、膨大な塩基配列の中では無視できない違いとなります。ただし現代社会では、すべての多様性に対応した環境が整っているわけではなく、いくつかの“型”に当てはめるような社会構造の中で、我々は生きています。
「教育」についても、本書では面白い視点が述べられています。
現代の教育は、単なる学習の枠にとどまらず、社会的なルールや文化的背景を含めて構成されています。しかしながら、教育と遺伝はしばしば「水と油」のように捉えられがちです。
遺伝的なものは教育できない、教育できるものは遺伝的ではない、そんな図式に囚われてしまいがちですが、実際にはそう単純ではありません。人間は「遺伝的に教育する動物」であると述べており、教育環境がその人の遺伝的な特質を開花させる可能性を持っている、と述べています。
■「才能」は、遺伝だけでは決まらない
最後に、「才能」の話が非常に興味深いものでした。
たとえばアスリートの場合、スプリンターにはRR型の遺伝子を持つ人が多く、持久系の競技にはXX型が向いている――オリンピック出場選手の遺伝子を調べた結果、そのような「傾向」があったことを示す研究結果も、たしかにあります。(いわゆる、速筋と遅筋という話ですね)
しかし、これをそのまま「営業職」などに当てはめたときは違います。
営業で成果を上げる人には、ルックスが魅力的で成績を上げる人もいれば、大量の数をこなして結果を出す人もいる。あるいは、豊富な知識や戦略で差をつける人もいます。つまり、同じ“成果”でも、その道のりは多種多様であるわけです。
だからこそ、遺伝子から“営業に向いているかどうか”を判断するのは、ほとんど不可能だということが分かります。そして、社会の役割とは、政治家で園芸家でもアーティストでも事務職でもマネジャーでも、同じように色々な登り方があるわけです。
■まとめと感想
結局、私達の身体的特徴から心や行動まで遺伝の影響は確かに存在しますが、それをどう発揮させるかは、やはり個々の試行錯誤や環境との相互作用に委ねられているわけです。
才能=遺伝ではなく、自分自身の“向き・不向き”を知るためには、実際にやってみること、試してみることが何よりも大切であり、それしか見つける方法はない、といっても過言ではないことを、改めて確信した一冊でした。
改めて「生まれ持って人は、なぜこうも違うのか?」という幼少期から持った疑問がありましたが、「遺伝の影響の中で、最大に踊れる場を探すのみである」ということを受け入れ、人生に向き合うべきということに、大切な示唆を与えてくれた本でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>