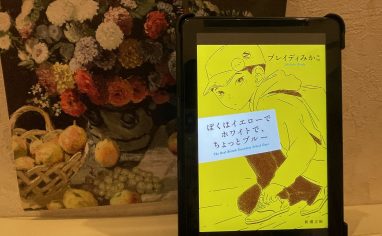「うんち展」で感じたこと・学んだこと
(本日のお話 2230字/読了時間3分)
■こんにちは。紀藤です。
さて、先日の日曜日、家族で東京ドームシティで開催されている『うんち展』なるものに行ってきました。
=====================
「うんち展 -No UNCHI,No LIFE-」
=====================
「うんちなしでは生きられない」
「No UNCHI、No LIFE」
イベントのサブタイトルを伝えるだけで、爆笑する息子(4歳)。
なぜ「うんち」には、こんなに魅力があるのか。
改めて考えてみると、こんなに身近で、こんなに人類共通で、こんなにパワフルなキーワードは、類を見ない気もします。
ということで、せっかくなので家族で一緒に勉強しに行こうということで、出かけた次第です。今日は、このイベントからの学びと気づきを、皆さまに共有させていただきたいと思います。
(正式な「うんち展」の表記を尊重し、伏せ字はせずに表現いたします)
それでは、どうぞ!
■なぜ子どもは「うんち」と言いたくなるのか?
そもそも、なぜ子どもは「うんち」と言いたくなるのでしょうか?
調べてみると、そこには5つほどの理由があるそうです。
どれも、心理的・発達的背景に由来する意外と大事な理由だとかなんとか。
1つ目は、「言葉の響きの面白さ」。リズミカルで発音しやすく、子供たちにとってはオノマトペ的な魅力があります。「ブリンバンバンボン」(byCreepyNuts)などのリズム言葉は、息子にも大ヒットしていましたが、リズムや音の面白さでは同じジャンルに入る気もします。
2つ目は、「禁じられた言葉を口にするスリル」です。大人が「そんなこと言っちゃダメ!」と反応することで、子供にとっては特別な言葉となり、余計に使いたくなるということです。
3つ目は、「自分の身体や排泄への関心」です。自分の身体をコントロールできる感覚と関係しており、それが興味の対象になるということもあります。
4つ目は、「友達とのコミュニケーション手段」です。お互いに「うんち」と言い合うことで仲間意識を感じ、一体感が生まれるようです。また、笑いが起こることで、さらにその言葉を繰り返し使うようになります。
そして5つ目が、「メディアや絵本の影響」です。『うんちドリル』などが広く知られており、それが子どもたちの興味を引くことにも繋がっているようです。
うんち展にいく下準備として「うんちの言葉の奥深さ」を調べてみましたが、確かに納得するものも多く、なるほどな・・・と勉強になったのでした。
■『うんち展』は科学展だった
さて、実際の『うんち展』がどんなものだったかというと、「想像以上に真面目な科学展だった」というのが結論です。入り口からしてまるで生物教室。
「No UNCHI、No LIFE」というコミカルなキャッチフレーズは、決して言い過ぎでもなんでもなく、世界を織り成す一端を描いているようにすら思いました。入り口からしてまるで生物教室のようでした。
まず「序章 うんちができるまで」では人体模型を通して、食道から胃、十二指腸、小腸、大腸、直腸を経て排泄されるまでの仕組みがリアルに展示されていました。
また草食動物は植物を消化するために腸が長いことが、実際の乾燥標本を通して示されていたり、ツキノワグマやタヌキなど、他の動物との消化器官の違いも説明されていたり、興味深かったです。(ちなみにそれぞれのうんちの模型は全部本物です/凍結乾燥)。
他にも自然界にある様々な動物のうんちも展示されています。世界各地の動物の剥製と一緒に並べられており、まるで動物園にいるようでした。
さらに、生物がうんちをどのように利用しているのかという展示もありました。よく知られている種の運搬や縄張り主張だけでなく、仲間同士のコミュニケーション、毒素の排出、土壌の肥沃化、さらには敵を欺く擬態や巣作りまで、多岐にわたる活用法が紹介されており、非常に興味深かったです。
■人の「うんち」のゆくえ
個人的におすすめの見どころは「人間のうんちの行方」でした。
具体的に、「野糞をすると、生態系に何が起こるのか?」という時系列の写真が興味深かったです。
実は野糞をすると、アリなどの昆虫が集まり、それから菌類が入り込み、やがて多くの生物が集まり始めます。まるで、そこは映画『もののけ姫』のラストシーンのシシ神さまの生命の風が吹き抜けた後のような、生命の萌芽が野糞の周りに生まれていて、感動すらしました。
現代社会では下水処理施設が整い、ろ過され、汚泥となったものは焼却され、処理されます。しかし排泄物も、重要な栄養素として自然界で循環していることを理解すると、なんとなく、一つの重要な連鎖が断ち切られているような感覚もします。
かつて肥溜めなどを利用し、農作物の肥料として経済システム・自然界の循環システムに組み込まれていました。素人考えですが、近代は科学によって、自ら循環を生み出そうとしているようにも見えます。ただ、同じパイの栄養素を自然と循環させるのではなく、人工的に作り出すことで、持続可能な世界を作れるのだろうか…そんなことも考えさせられたのでした。
■まとめと感想
率直な感想は、「めっちゃ勉強になった」ということ、そしてこれほどまでに記事内で「うんち」を連発したのは初めてであった、ということです。(不快に感じられた方、申し訳ございません)
ちなみに全くの余談ですが、本記事は音声入力で文字起こしをしていたのですが、Windowsの文字起こし機能が「うんち」を「***」という伏せ字に変換することに初めて気がつきました。音声入力だと、放送禁止用語のような認識がされているのですね。
ご興味がある方は、おすすめです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
※本日のメルマガは「note」にも、図表付きでより詳しく掲載しています。よろしければぜひご覧ください。
<noteの記事はこちら>